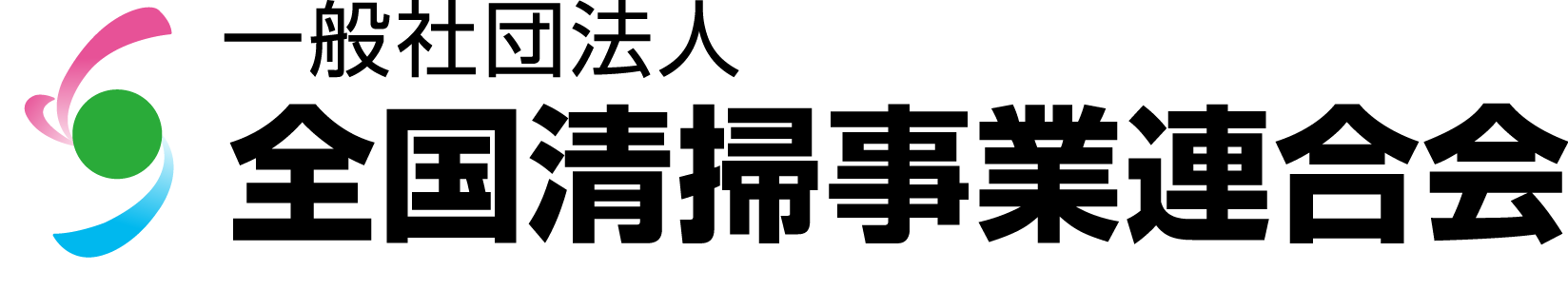-

平成26年度の総会の報告
続きを読む: 平成26年度の総会の報告全清連・第五回定時社員総会開催
~6.19通知の浸透に向けて強い決意~
一般社団法人全国清掃事業連合会(全清連・三井崇裕会長)は4月18日(金)午後1時半より千代田区の如水会館において、第5回定時社員総会を開催した。冒頭、全清連を代表してあいさつに立った三井会長は、平成20年に環境省が6.19通知を発出したにもかかわらず、新規許可の乱発あるいは委託業務を随契から入札に変更する市町村が増加していることを重くみて、「今年度は何が何でも正常化していかないといけない」と、出席した230余名の会員を前に強い決意を語った。総会終了後には環境省廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課の松田課長補佐の講演が行なわれた。また席を移しての懇親会は地域廃棄物適正処理推進議員連盟会長の石破茂自民党幹事長、副会長の斉藤鉄夫公明党幹事長代行、事務局長の野田聖子自民党総務会長らをはじめ多数の国会議員、省庁幹部らが出席しての和やかな祝宴となった。
廃掃法の正常な理解へ

第5回となる定時社員総会は、開会に先立ち全清連の「連合会旗」が入場。全員起立し大きな拍手で迎えた。正面には国旗ならびに全清連の連合会旗が掲げられている。これに向かって一同君が代を斉唱して総会は幕を開けた。
全清連を代表して三井会長があいさつ。平成10年に発足した全清連は今年度で17年目を迎える。三井会長は発足時から今日までを振り返り、「この16年間、ことあるごとく外圧によって廃棄物処理法の定義・区分が壊されようとすることに多々直面したわけでありますが、私どもは全員の力でそれを阻止し、現行廃掃法の地域の環境を守る、そして公衆衛生を確保するために我々は努力してきたわけです。このことは譲れるところではありません」と強調。しかし区分見直し論は、「各種リサイクル法の運用に際して、今でも出てきている」と気を引き締める。
また、新規許可を乱発する、あるいは委託業務を随契から入札に変更する市町村が増加しつつある現況について、環境省が平成20年6月19日に発出した6.19通知があるにもかかわらず、新規許可を乱発し、随契を入札に変える市町村も見られる。「当該市町村にお会いして説明申し上げても聞いていただけない」ことから、2月14日に自民党の石破幹事長を会長とする52名の衆参国会議員からなる全清連の議員連盟との懇談会の席で2つの案件を要望したことを説明。「26年度は大きな問題を抱えています。どうしてもこのことはカタをつけていかなくてはいかんと思っております。全清連執行部体制の中で、何が何でもこのことは正常化してもらわないといけないと意見の一致を見ております」と強い決意を語った。平成26年度の事業計画
このあと議長に大月伸一副理事長(新潟県一般廃棄物処理業者協議会)を選出し議案を審議。原案通り満場一致で承認可決し総会は滞りなく終了した。
平成26年度の事業計画は、基本方針を踏まえて以下の6つを示した。
①廃棄物・リサイクル制度に関する対策活動
②地方における地域生活環境保全、公衆衛生確保向上のための対策活動
④全清連の組織充実強化と団体会員拡大のための活動
⑤地域廃棄物適正処理推進議員連盟との連携強化ならびに支援強化のための活動
⑥会員の啓発ならびに広報のための活動
⑦東日本大震災の被災地への支援活動の経験を活かした活動石破議連会長「容リ法での材料リサイクル50%優先枠は守る」

総会終了後には環境省廃・リ部廃棄物対策課の松田課長補佐の「一般廃棄物処理に関する今後の取組みについて」というテーマで講演が行なわれた。会場を移しての懇親会では全清連議連の会長をつとめる石破茂自民党幹事長が駆けつけあいさつを述べたほか、議連副会長の斉藤鉄夫議員、事務局長の野田聖子議員ら多数の国会議員や省庁幹部のあいさつが続いた。
石破議連会長は「(容リ法でプラ容器包装の材料リサイクルに与えられている)50%優先枠は、それぞれ頑張っておられる会社さんのご努力を無にしないためにも、地域における活動を活発化させていただくためにも、この優先枠は守っていかなくてはならないと思っております」と力強い言葉。
乾杯の発声は前衆議院議員で全清連特別顧問の中川秀直氏。「皆さんと先頭に立って循環型社会をつくっていくんだという誇りをもってやっていきましょう」という掛け声とともに出席者一同高く杯を上げ、和やかな祝宴が繰り広げられた。総会の詳しい内容については「全清連ニュース71号」をご覧ください。
第五回定時社員総会開催 資料 <会員限定>
-

平成25年度の全国研修大会実施報告
続きを読む: 平成25年度の全国研修大会実施報告平成25年度『全国研修大会』を盛大に開催
一般社団法人全国清掃事業連合会(全清連・三井崇裕会長)は10月23日(水)午後1時より東京千代田区の砂防会館において全国から630余名の会員が出席し、平成25年度の「全国研修大会」を盛大に開催した。研修大会は第一部・全清連三井崇裕会長ならびに議員連盟、各省庁のあいさつ、第二部・地域活動の事例発表、第三部・記念講演、当面の事業方針、招待団体等紹介、大会決議、スローガン採択――からなる三部構成で進められた。昨年12月の衆院選挙さらに今年7月の参院選挙の結果、自公が大躍進を遂げ磐石な政権与党が誕生したことは改めて言うまでもない。これにより全清連議員連盟へのご加盟も増え、衆参の国会議員49名の先生方で構成されることとなった。三井会長は冒頭のあいさつでこのことに触れ「非常に強烈な議員連盟の形ができました」と、全清連の組織が強固なものになったとの認識を示した。また地域活動の事例発表では熊本県清掃事業協議会の廣田専務理事が、同協議会への会員加入促進策を報告し、さらに講師に磯﨑参議院議員を迎えての講演では、議員になる前の自身の民間企業勤務時代の経験を織り交ぜながら、一般廃棄物処理業の性格ならびに全清連活動に期待することを語った。当面の事業方針では全清連の山田専務が、産業界ばかりでなく最近では「市町村側から一廃・産廃のなし崩し的な区分変更の事案が多く生起している」と指摘し、それへの対応として「廃棄物処理法の解説」をもとに一廃・産廃の区分についてのポイントを示した。研修大会は中身が濃いものとなり、出席者は熱心に聞き入っていた。

強烈な議員連盟が構成され、全清連の組織も強固なものに

研修大会は歌手中島みゆきの「地上の星」のインストルメンタルが会場に流れる中、盛大な拍手に迎えられ全清連の連合会旗入場でスタート、次いで全員が起立して国歌が斉唱された。
全清連を代表して三井会長が壇上に進みあいさつ。今年の7月末から8月初旬にかけてのゲリラ豪雨により山口市では災害が発生し、地元の前田理事長が早速準備して災害除去を展開した。また9月には同様に京都府がゲリラ豪雨に見舞われ、福知山市では山本会長以下、率先して災害支援の準備をし、東海、近畿ブロックからも全清連会員が馳せ参じ災害復旧のために奮闘した。これらはいずれも無償支援活動として行われたもので、この活動に関して三井会長は冒頭、「私どもの行動の展開でした。皆さんにご報告申し上げたいと思います」と述べた。また昨年12月の衆院選と今年7月の参院選の結果、自公による完全制覇が達成されたことについて「全国の会員の皆様にご支援のお願いをしてきたことでありますが、この席をお借りしましてお礼申し上げる次第です」と感謝し、続けて「中川秀直先生が議員を引退しました関係上、新しい議員連盟は会長に自民党の石破茂幹事長に就任をお願いいたしました。副会長には自民党の竹本直一先生と公明党の斉藤鉄夫先生に、そして事務局長には野田聖子先生にお願いいたしました」と地域廃棄物適正処理推進議員連盟の新陣容を報告。加えて「中川先生にはこの4月の総会で特別顧問をお願いしましたところ、快くお引き受けいただきました。また前環境省事務次官の南川秀樹先生にも特別顧問を快諾していただきました」と述べた。
全清連の議連は「現在49名の衆参の先生方で構成されていることをご報告申し上げます。非常に強烈な議員連盟の形ができたわけです」とし、全清連の組織が一段と強固なものになったことを強調した。規制を緩めればいいというものではない

議員連盟ならびに関係省庁から多数のごあいさつ、ご祝辞をいただいた。議員連盟は代表して会長の自民党石破幹事長が「環境というのは基準を緩めるとあまりいいことはありません。法律はそれなりに良く出来ているのでありますが、それを誰がどのように運用するかで結果は全く異なってまいります」と述べ、小型家電リサイクル法にしても附帯決議が付けられていることを示し「それがきちんと運用されなければこの法律は機能することはございません」と法の運用がいかに大切であるか指摘し、「儲かればいいやという人が入ってくる。技術の低い人が入ってくる。これは規制緩和の名の下に環境がわるくなり、公衆衛生がわるくなる」と警鐘を鳴らす。「私どもとして、何でもかんでも規制を緩めればいいとは思っていません。特定の団体、特定の企業を保護するという考えには基づいていません。どうやって環境を守り、どうやって公衆衛生を守るのか、そのためにはどう法を運用していくか。我々議連としても誤りなきようしたい」と法の運用のもとでの環境優先の考え方を述べた。
議連の竹本副会長、斉藤副会長、野田事務局長らをはじめ衆参30名の先生方からのごあいさつが続いた。環境省、経産省、農水省の幹部からのごあいさつ、中川特別顧問、南川特別顧問からもごあいさつをいただいた。地域活動の事例報告・熊本県の会員加入促進の取り組み
休憩を挟んでの第二部は地域活動の事例発表。今回は熊本県清掃事業協議会の廣田専務理事による「熊本県における会員加入促進の取組みについて」が報告された。
報告者の廣田氏の会社はし尿処理から出発し、ごみ処理に転換して通算50年の歴史がある。廣田氏自身は大学を卒業後、東京でサラリーマンをしていたが、その後家業を継ぐため帰省する。ところが実家の経営状態が破綻に近いことを知る。廣田氏は廃棄物関係の本を読み漁った。「こんなに法律に守られているのに経営が厳しいのはなぜか。委託金額が低かった。委託料が委託業務に遂行するに足りる額であること。法律にはこう書いてあるのに……。この矛盾に悩んでいた」(廣田氏)。
そんなとき、福清連(福岡県清掃事業協同組合連合会)の西山会長(当時)の訪問を受ける。これをきっかけに未組織であった同業者の組織化へと進んでいく。「約2年間にわたり毎月1回行なわれていた福清連の会議にオブザーバーとして出席させてもらった」。ここで廣田氏は様々なことを学び取っていく。組織化については同業者にDM(ダイレクトメール)を送付し、思いを伝えた。また行政に対してはトップや部長にあいさつを恒例化するなど様々な活動を展開する。多くの紆余曲折はあったものの、組織は3年間で28社になり、今後の加入も見込めるようになった。組織ができて情報も集まってくるようになった。また行政に関しては環境についての定例会議を設けることができ「原動力になった」という。講演会・全清連活動に期待すること

講師に議員連盟の磯崎仁彦参議院議員を迎えての講演「全清連活動に期待すること」は、自身が航空会社(ANA)企業勤務時代の経験を織り交ぜながら、一般廃棄物処理業の性格ならびCSR(企業の社会的責任)を説明しつつ全清連活動に期待することを語った。一廃処理業とはどういうものなのか、社会の中での位置づけをきちんと整理分析しつつ、求められるものについて言及したこの講演は、傾聴に値するものとなった。
まず今年7月の米国デトロイト市の財政破綻とナポリのごみ問題をトピックとして取り上げた。財政破綻に陥ったデトロイト市では債務カットなどを通じて必死に再建に取組むが、そんな中でスナイダー知事は「警察や消防、ごみ収集、街灯を例に挙げ、行政サービスの投資は続ける意向を示した」という。「削っていいものは削っていくが、ごみ収集とかは削ることができないと(知事は)主張している。市が財政破綻しても国民の生活に密着していることは守っていく。これは大きな意味がある」(磯崎議員)。
つまり一廃処理業者の仕事は「生活に密着している。何かあったときにクローズアップされるのではないかと思う」。
一廃処理業の性格とは、「何か起こらなければ住民にとって自然と流れていく、いってみれば空気のような存在。しかしサービスが停滞すると住民の生活に大きな影響が出る」。ごみの収集は直営と委託があるが、基本として「税により運営されている公共サービス。税が投入されていることから、住民の見る目は厳しいものがある」と自覚を促す。日常の中で「皆様の活動が表に出てくることはない」。しかし社会的貢献は必要になってくる。なぜ必要なのか。磯崎議員はCSRの考え方やコンプライアンスといったことをANA時代の経験などをもとに語った。当面の事業方針
研修会も終盤にさしかかり、全清連・山田専務が当面の事業方針を問題提起という形で発表した。固形一廃業界にとって、いま最も重要な問題は、中央において廃棄物処理法の定義・区分を改悪しようという動きであり、「その動きは弱まっていない。政府の規制改革会議だけでなく、食リ法や容リ法、小電法などにおいてもその傾向が見える。廃掃法がじゃまだという論法です。そのため廃棄物を循環資源とか副産物という言い方をする。だから廃棄物ではないという論理を展開する」と指摘。
地方に目を向けると、入札の導入、許可乱発の事案に加え、「市町村行政側から行なう一廃・産廃のなし崩し的な区分変更の事案が多く生起しているということです」(山田専務)。市町村行政側から行なう一廃・産廃のなし崩し的な区分変更の事案のひとつの例をあげる。サラリーマンが事務所でポリ袋に入っているパンを食べた。そのポリ袋は産廃になるということを言い出している市町村が出てきた。「市町村は要するに、ごみを減らしのため一廃を産廃に付け替えようとしている。統計上は減量になる。すると一廃業者はたまったもんじゃない」。こうしたことにどう対応していくのか。「廃棄物処理法の解説」(平成24年度版)では、産業廃棄物について、量的又は質的に環境汚染として問題とされる……と書いてある。「サラリーマンが食べたパンのポリ袋は環境汚染になるのか」と述べ、なぜ廃掃法が制定されたのか。その社会的背景はどうなのかといった事柄について、「廃棄物処理法の解説」をしっかり読み込む必要があるとした。また「業務品質の向上を表に出す。自分たちの仕事は掃き清める仕事であるということを外部にアピールしないと、行政に抗議しても受け止められない」と述べた。
研修大会は最後に大会決議、スローガンを採択して幕となった。
(研修大会の詳細は、11月下旬発行予定の全清連ニュース第69号に掲載)。 -

平成25年度の総会の報告
続きを読む: 平成25年度の総会の報告全清連・第四回定時社員総会開催
~会長に三井崇裕氏を再任~一般社団法人全国清掃事業連合会の第四回定時社員総会は4月19日(金)午後1時半より東京千代田区の如水会館で開催され、任期満了に伴う役員改選では会長に三井崇裕氏の再任をとりきめた。社員・オブザーバーを含め総勢230余名の出席者を前に三井会長は「全清連の組織を強固なものとし、業界を維持するためにも皆様とともに頑張っていきたい。どうぞよろしくお願いいたします」と協力を求めた。総会終了後には環境省リサイクル推進室の永島室長の特別講演が行なわれた。またそのあとの懇親会は地域廃棄物適正処理推進議員連盟会長の石破茂自民党幹事長、副会長の斉藤鉄夫公明党幹事長代行、竹本直一自民党財務金融部会長、事務局長の野田聖子自民党総務会長ら議連三役をはじめ多数の国会議員、省庁幹部らが出席して開かれ賑やかなものとなった。

常について回る廃掃法の定義・区分の問題
総会では司会を林和幸常任理事(岐阜県清掃事業協同組合)が務めるなか、今回作製した全清連の「連合会旗」が入場。全員起立し大きな拍手で迎えた。正面には国旗ならびに全清連の旗掲げられ、これに向かって一同君が代を斉唱して総会はスタートした。
まず全清連を代表して三井会長があいさつ。全清連は結成以来15年を経るが常に廃掃法の定義・区分の問題がつきまとっている。それについて三井会長は昨今の情勢を織り交ぜながら次のように語った。
「小型家電リサイクル法にも区分のところに抵触する論点がありまして、これは看過できないということで私ども、環境省と経産省に厳しく追求申し上げました。議連の先生の方々にもご相談し、我々執行部体制の下で議論に議論を重ねた。で、基本方針、ガイドラインでかなり絞込みがありましたので了解に達したわけです」。今年度は容リ法、食リ法の見直しの時期にきているが、ここでも必ず大きな議論になるのが区分の問題。「容リ法にしても経産省と環境省の合同で審議しましょうということになっている。しかし一方で政府の規制改革会議があって、そこで経団連の方々の力が働く。廃掃法の区分のところがじゃまになるんですね。あんなもの取っ払ってしまえという乱暴な提言がされている。それを許してしまうと我々が市町村からいただいている委託や許可がなし崩し的に無用化されてしまう。廃掃法の行方が非常に危ない」と危機感をあらわにする。
全清連は着実に前進している。
しかし「私どもには議連があります。昨年の選挙で自公が勝利したことにより、これまで26名だった議連の先生方は衆参あわせて41名という大きな組織になりました。全清連がそれだけ政治力を有したということです。しかも会長には自民党の石破幹事長が決まりました。副会長には公明党の斉藤鉄夫先生と自民党の竹本直一先生、さらに事務局長には野田聖子自民党総務会長という三役です。これは15年間頑張ってきた全清連の力なんです。皆さんの力なんです。皆さんに支えていただいたからこそこういう形になってきたと当然思っています。全清連は着実に前進しています。全国組織として力を蓄えてきたと私は受け止めています」と締めくくった。

平成25年度の事業計画
このあと議長に大月伸一常任理事(新潟県一般廃棄物処理業者協議会)を選出し議案を審議。第一号議案~第五号議案を原案通り満場一致で承認可決。第六号議案の役員改選の審議に入った。理事候補者が別室にて協議した結果、会長に三井崇裕氏の再任をとりきめたほか、新執行部役員を選出した。再任となった三井会長は「全清連の組織を強固なものとし、業界を維持するためにも頑張りたい」とひとこと述べ、総会は滞りなく終了した。
平成25年度の事業計画は、内外の政治経済情勢、環境分野に対する規制緩和の動向、環境省他各省庁の動向、地方における動向などに広く注意を向け、いち早く情報の入手に努め対応していくとし、具体的には基本方針を踏まえて以下の6つを示した。
①廃棄物・リサイクル制度に関する対策活動
②地方における地域生活環境保全、公衆衛生確保向上のための対策活動
④全清連の組織充実強化と団体会員拡大のための活動
⑤地域廃棄物適正処理推進議員連盟との連携強化ならびに支援強化のための活動
⑥会員の啓発ならびに広報のための活動
⑦東日本大震災被災地への支援の取り組みについて総会終了後には環境省リサイクル推進室の永島室長による小型家電リサイクル法を中心とした特別講演が行なわれた。場所を移しての懇親会では全清連議連の会長をつとめる石破茂自民党幹事長が駆けつけあいさつ。「容リ法のプラスチックにしても材料リサイクル50%の見直しというのが規制改革会議で議論されているやに聞いております。これ、いたずらに競争すればいいのか」と疑義を呈した。副会長の公明党斉藤鉄夫先生、竹本直一先生、事務局長の野田聖子自民党総務会長らをはじめとする多数の国会議員や省庁幹部の祝辞が続いた。乾杯の発声は前衆議院議員で全清連特別顧問の中川秀直氏。「全清連の一兵卒となって皆さんと頑張っていきたい。更なる発展をしましょう」と述べ出席者一同高く杯を上げ、和やかな祝宴が繰り広げられた。
総会の詳しい内容については「全清連ニュース67号」(5月下旬発行)をご覧ください。
第四回定時社員総会開催 資料 <会員限定>
-

平成24年度の全国研修大会実施報告
続きを読む: 平成24年度の全国研修大会実施報告平成24年度『全国研修大会』を盛大に開催

一般社団法人全国清掃事業連合会(全清連)は10月26日(金)午後1時より東京千代田区の砂防会館を会場に、平成24年度の「全国研修大会」を盛大に開催した。全国から600数十名の会員が参集した本研修大会は、メインスローガンに「東日本被災地復興への苦闘を思いつつ地域環境の保全活動に邁進しよう!」を掲げた。東日本大震災から1年7カ月が過ぎようとしているが、被災地は今この時期においても一部地域を除いて生活再建の目途も、産業復興の目途も厳しいといわれている。ようやく膨大な災害廃棄物の処理処分の目途が立った段階にすぎない被災地の人々の悲痛とも言うべき心情を思いつつ、まさに地域の生活環境の保全と公衆衛生の向上・確保というライフラインの維持そのものに深く携わる当事者として、直面する様々な問題の検討と分析を共有し、その解決に向けた取組みをしていかねばならない。
全国研修大会は、第一部・全清連三井崇裕会長および地域廃棄物適正処理推進議員連盟、各省庁のあいさつ、第二部・講演会、第三部・地域活動の事例発表、当面の事業方針、大会決議、スローガン採択――の三部構成で進行した。講演は環境省廃・リ対策部リサイクル推進室の眼目(さっか)佳秀室長補佐による「不用品回収業者対策」と「小型家電リサイクル法」。地域活動報告としては岐阜県清掃事業連合会が「岐阜県における不用品回収業者対策と業界の取組み」を、大阪市清掃連合協同組合が「大阪市における新規許可問題」といった、まさに業界が直面している問題についてそれぞれ報告。当面の事業方針は、業界を覆っている問題の根本部分には廃棄物処理法の定義・区分の見直しがあると捉え、さらにそれを深く分析すると例外なき「規制緩和」を推し進めようとする動きに行き着くとし、これまで規制緩和がどのように打ち出されてきたのか、歴史的検証を行ない問題提起とした。三井会長、全国2万1000社の同志のためにもこの組織を推進

演壇の上方部には日本国の国旗と全清連の連合会旗が掲揚されている。全員が起立し君が代を斉唱。参集者の心がひとつになったところで、全清連を代表して三井崇裕会長があいさつ。
「全清連ができて今回で15回目の大会を迎えます。節目の年といってもいいでしょう」と切り出した三井会長は、この15年間を振り返る。「様々なことが走馬灯のようによぎるのでありますが、年々感じるのはこの大会で皆さんとお会いするたびに、この組織は全国的に強固になってきているということです」と述べ、さらに15年間の中で議員連盟を結成したことをあげ、「(我々の業務は)環境省、経産省あるいは農水省などと関連が深いので、ことあるごとに関連省庁と問題を協議させていただく中で、議連の先生方に逐次ご報告、ご意見を述べさせていただき、その上で指導をしていただくということがずっと続いてきています。いろんな事柄の中で、問題解決をひとつずつやり通して今日まで来ました。この大きい力は本日、全国から集まっていただいた会員の皆様の私ども執行部に対する支持があったからこそでございます。ほんとうにお礼申し上げます」と参集者に感謝の意を表した。さらに、全国に1719の市町村があるが、この中には「私どもの委託あるいは事業系一廃業者が約2万1000社いらっしゃる。私どもは委託、許可という名称ですが、一方では市町村長さんの代行者でもあると思うんです」。つい先般、小型家電リサイクル法が制定されたが、「小型家電の収集運搬は現場のプロである我々全国の2万1000社にお任せいただいてもいいんじゃないかと最近思っております」と新たなリサイクル制度に対して注文をつけた。最後に「これからも年1回の研修大会は続きます。全国2万1000社の同志に対しても頑張ってもらえるよう、我々の組織を推進していかなくてはならないと思っています」と結んだ。議員バッジを外しても全清連を応援すると中川議連会長
議員連盟からは、衆議院議員の中川秀直議連会長、西野あきら議連副会長、石破茂衆議院議員、野田聖子衆議院議員らを含め多数の衆参国会議員が列席。中川議連会長は使用済み小型家電リサイクル法について触れ「これについてはいくつかの懸念がございました。認定事業者が市町村主体でない形で集荷をはじめて、そして皆さんの毎日やっておられる一般廃棄物の処理事業、これとまた別枠の姿で進んでしまうのではないか。それはかえって新たな混乱を引き起こしはしまいかと。この小型家電リサイクル法については本日ご列席の先生方が集まってくれまして、全清連の方々も一同に集まり、そこに行政も加わって議論を致しました。その結果、法律の附帯決議で、市町村が主体となった回収構築のために国は努力しなさい。そして認定事業者、委託業者の指導監督については認定の取消しもある。再委託は認めない。また地域に根づいた回収業者の有効な活用を図ることなどが盛り込まれて、このことについて環境省からもしっかりした見解の表明を我々の会合の中でお示しいただいた」と述べた。また今夏、プラ容器包装のマテリアル再商品化施設である広島リサイクルセンターを視察。環境省、経産省の担当官を交えて議論を行い「3Rの順に取り組んでいくことの原則を確認した」と、容リ法見直しに向けての意見を語った。
最後に中川議連会長は、「世代交代をする時ということで、次期総選挙には不出馬を決断させていただきました。しかしバッジを外しましてもまた、これからも全清連を応援する形でかかわらせていただきます」と力強い言葉で締めくくった。
石破茂自民党幹事長は、しばらく前に起きた東北自動車道のバス大事故を例に挙げ「安くてもいいや、どんなもんでもいいやとなると世の中大変なことになる。ましてや廃棄物処理の世界にこうした原理を導入することは極めて誤りであって、どんな世の中にあってもきちんとした業がなされないといけない」と廃棄物処理の世界に、安かろう悪かろうがあってはならないと述べた。
このあと、環境省、経産省、農水省の各省の幹部によるあいさつが続いた。

講演、不用品回収業者対策と使用済み小型家電リサイクル法
第二部の講演は、環境省リサイクル推進室の眼目(さっか)室長補佐による「不用品回収業者対策」及び「使用済み小型家電リサイクル法」について。各自治体でも手を焼いている不用品回収業者対策については、環境省が今年3月19日に都道府県を通じて各市町村に通知した「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断」に基づき、積極的にパトロールを行い、立入り検査や指導を実施する自治体が増えつつあるが、その一方で及び腰になっている自治体もあるとし、「不用品回収業者は法令を知らないケースもあるので及び腰にならないで積極的に指導してもらいたい」と要請した。今年9月から10月にかけて、立て続けに7件もの金属スクラップの火災が港や船で起きている。「環境省だけでなく、海上保安庁、警察、税関も非常に深刻な問題として受け止めている」と、この問題の重大性を指摘。環境省の権限としては廃棄物に該当する者については大臣の確認を受けなければならないという廃棄物処理法の規定により、「地方環境事務所にパトロールして指導、取締りを強化していく」と述べた。「市内では市町村が頑張る。水際では環境省が頑張るといった2つの面で取り組んでいきたいと」示した。
使用済み小型家電リサイクル法については制度の仕組みを説明。現在検討会で政省令を審議中だが、対象になる小型家電は「約280品目ぐらいあると考えている」と品目数について触れた(小型家電リサイクル制度の検討会の様子については全清連のHPに記載。講演の詳細は全清連ニュースをご参照ください)。岐阜県と大阪市から地域活動の事例報告を発表
第三部は地域活動の事例報告。岐阜県と大阪市からそれぞれ発表された。
岐阜県清掃事業協同組合(岐清協)
岐阜県清掃事業協同組合(岐清協)は山口常任理事が「岐阜県における不用品回収業者対策と業界の取組みについて」報告。取組みのきっかけとなったのは平成16年ごろ。一般廃棄物の許可をもたない業者が、まちの便利屋と称して、新聞のチラシや無料冊子、ポスティングなどで家庭ごみの処理を代行すると宣伝していた。それが年々拡大していった。「無許可営業で一部は有料で回収するといっていた。これでは不適正処理によって地域の環境が脅かされる。なによりも、このような悪質業者と私ども許可業者が同等に見られる」(山口常任理事)ことに岐清協は強い危機感を抱く。当時の岐清協の対応は、違法と思われる業者の確認、広告の文言等をチェックして個別に市町村を訪問。悪質な業者にごみ処理を依頼しないよう広報等で住民啓発のお願いを要請した。しかし不用回収業者数は増大して、高額な処理費の請求もみられるなど苦情やトラブルも発生していた。
そうこうしているうちに平成21年にリサイクルショップ併設のまちの便利屋代表者が廃棄物処理法違反で逮捕される。岐清協は市町村に対して立ち入り調査を要請してきたが、平成22年10月に環境省から通知が出され、市町村の立入りの権限が出来た。しかし立ち入り出来てもそれ以上の指導が出来ないという状況だった。そこで岐清協はこの問題を全清連に上げ、全清連議員連盟から環境省に働きかけてもらい今年3月19日に環境省から廃棄物の該当性の判断が発出された。
岐清協はこれをもって各市町村を訪問。立入り調査、指導を要請する。市町村もこれに応じて取組みを始めた結果、3.19通知前には岐阜県下で162の無料拠点回収があったが、今年9月時点では100拠点に減少した。「無許可不用品回収業者が減ってきたとはいえ、まだ営業している業者もいる。行政と連携して対応していきたい。3.19通知を有効に活用して、各県連にあった形で取り組んでいただけたらと思う。ただこうした持込み回収に対して市民は、いつでも持込めるとか時間に融通がきくといった利便性も感じている。業界としてもいかにサービスを向上させていくか検討する必要がある」と山口常任理事は課題も含めて述べた。大阪市清掃事業連合会
大阪市清掃事業連合会の木村理事長からは「大阪市における新規許可問題について」という、現在進行している問題が報告された。これについては当連合会のホームページに掲載したように、9月1日に大阪城公園内音楽堂で業界関係者約2500名が参集しての「怒りの決起集会」が挙行されたので参照されたい。大阪市は昨年11月の市長選挙で、維新の会を率いる橋下市長が誕生。議会も維新の議員が過半数を占めるに至った。大阪市の公務員数は約3万9000人。人口割にすると他自治体より多い。これを約半分の1万9000人にすることを橋下市長はマニフェストに掲げて当選を果たした。「当初は水道局、交通局など諸々、人員削減という形で動かれておったのですが、環境局にもメスが入るようになった」(木村理事長)。ここから環境局は、収集運搬部門の「非公務員化」という施策を打ち出す中で許可業者を巻き込み、「新規許可付与」という動きに走る。
大阪市の許可業者数が多い。業者の経営基盤の強化、民営委託の強化、減量・リサイクルの推進などを進めるため、環境局は業者削減のための許可要件をペーパーで示した。そのなかに、「新規許可付与」という文言が付け足しのように差し込まれていた。
許可業者が飽和状態なのに新たに新規許可を出す。これでは非常に混乱を招くし、安全・安心な処理が担保できない。こうした環境局の施策に業界は当然納得できない。じつはこの新規許可付与には環境局の裏の理由があるのだが、それはともかくとして業界は様々な活動を展開し、現在、議員連盟を結成して対応している最中。来年4月には新規許可の試験が予定されている。
この半年間、業界はいろいろ動いてきた。その経験から木村理事長は次のように語る。「もし大阪市に新規許可が出て、全国の自治体に飛び火するようなことになったら、ぜひ皆さんの地元の若い経営者の声に耳を傾けてやってください。今まで数十年この業界に非常に長い間おられた諸先輩方、いろいろ経験されて口では言えないものを身につけています。しかし、ただ時代が違います。その方たちが経験されてきた遠い昔の時代では、ものの考え方、行政側の考え方が非常に変わってきています。諸先輩方の余力があるうちに、若い人たちに経験を積ませてやってください」。当面の事業方針、規制緩和の不合理性を十二分に理解すること
事例発表のあとは当面の事業方針を山田専務理事が説明。「事例報告発表は固形一廃廃棄物処理事業者が直面している事柄の一端に触れたのではないかと考えます」。山田専務はこう語りだし、「やはり根本問題は、廃棄物処理法の定義・区分の見直しにかかる問題であり、これを突き詰めていくと規制緩和の問題ではないかと考えられます」と論を進める。たとえば大阪市の新規許可問題にしても、「その根っ子には、公共サービスとしてのごみ収集運搬業務に果てしないダンピング競争を持ち込んで、そこに働く人たちを追い詰めても良いとする弱肉強食の論理が見えます」と、規制緩和がもたらす劇薬効果を指摘。
そして、規制緩和の源流とも言うべき平成5年の当時の細川内閣で設置された経済改革研究会で打ち出された「中間報告」を紹介。さらに平成10年の小渕内閣、平成13年の小泉内閣でも規制緩和が推進された。小渕内閣の時代にはオリックスの宮内社長(当時)が委員長を務める「規制緩和委員会」が発足し、平成10年にはこの規制緩和委員会が市町村のごみ処理を民間開放せよ、許可制ではなく届出制で業が出来るようにせよという方針が日経新聞に取り上げられ、これに危機感を強くした一廃業界約1000名が総務省に押しかけ、これは白紙となったが、これを期に現在の全清連が結成される。しかし翌年には事業系一廃を産廃にするという区分の見直しが浮上してくる。その流れは今でも続いている。止まってはいない。
このように規制緩和推進論者は虎視眈々とこの業界を狙っており、そのためには一廃業者も、廃棄物処理業になぜ規制緩和、市場原理を入れてはいけないのかをきっちり勉強、理解し、理論構築して行政や議員に接する必要があると問題提起した。
研修大会はこのあと、大会決議、スローガン採択と続いた。
(研修大会の詳細は、11月下旬発行予定の全清連ニュース第65号に掲載)。 -

平成24年度の総会の報告
続きを読む: 平成24年度の総会の報告全清連・第三回定時社員総会開催
~研修会を通じて学習を~一般社団法人全国清掃事業連合会の第三回定時社員総会は4月20日(金)午後1時半より東京千代田区の如水会館で、社員・オブザーバーを含め総勢219名の出席のもと開催された。全清連を代表してあいさつに立った三井崇裕会長は、各都道府県でトラブルが発生している不用品回収問題について触れ、「3月19日付で環境省から適正な指導通知が発出されている。このことは全清連の活動の大きな成果である」とし、平成20年の6.19通知と今回の3.19通知をリンクするなかで、各県や地域ブロックで実施している研修会を通じてこのことを学習してほしいと要望した。

不用品回収問題に関する環境省通知、研修会を通じて学習を

総会では司会を林和幸常任理事(岐阜県清掃事業協同組合)が務める中、全清連を代表して三井会長があいさつ。「本日は当連合会結成以来15年目の春を迎えることとなりました。一般社団法人化してからは第3回目の総会となります」と切り出した三井会長は、「全国の皆様方から絶大なる協力、ご支援を賜ったおかげで、こんなにもがっしりした全国組織として成長できたことについて厚く御礼申し上げます」と感謝の意を表した。さらに昨年の東日本大震災発生での全清連支援活動に触れ、「環境大臣の要請に基づき、皆様から多大なる拠出をいただきその力で岩手県大槌町を中心として、4月後半から5月中旬にかけて約3週間、支援活動してまいりましたが、この全清連のとった支援活動については、1年が経過した今でも関係各位から絶大なるお褒めの言葉をいただき続けています」と重ねて感謝した。全清連を取り巻く環境については種々あるなかで、とくに各都道府県でトラブルが多発している不用品回収問題については「これを何とか整理整頓すべきではないかと理事会で緊急課題として持ち上がり、3月19日付で環境省から適正な指導通知が発出されました。各政令都市などで不用品回収に対してのヒアリングが行なわれ、各県警の生活安全課も立ち上がって法律を守るように指導に入るという動きが出ているようであります。平成20年6月19日付けで発出された内容、そして今回の不用品回収は法的根拠に則って整理整頓しなさいということが出されたわけです。このことは全清連の大きな活動の成果であると思っています」とし、「全国で実施している研修会を通じて、6.19通知ならびに3.19通知をリンクさせるなかで、学習していただきたい」と要望した。
平成24年度の事業計画
このあと議長に大月伸一常任理事(新潟県一般廃棄物処理業者協議会)を選出し議案審議。①第一号議案・平成23年度事業報告~⑤第五号議案・平成24年度収支予算案を満場一致で可決承認した。
平成24年度の事業計画は固形一般廃棄物を取り巻く情勢として、内外の政治情勢、環境分野に対する規制緩和の動向、環境省ならびに地方における動向など様々な面に目を向けることが必要とされる。なかでも「使用済み小型家電リサイクル法案の提出」「容器包装リサイクル法の見直し審議」「地方自治体における事業系一廃の区分取扱い」――については、環境省に対して言うべきところは素直に意見していく姿勢を貫いていき、地域の生活環境保全と公衆衛生確保向上のスキームを堅持するためには一歩も退かない気概で臨む。
各事業の活動方針としては基本方針を踏まえて以下の6つを示した。
①東日本大震災被災地の復興支援の取り組み
②廃棄物・リサイクル制度に関する対策活動
③地方における地域生活環境保全、公衆衛生確保向上のための対策活動
④全清連の組織充実強化と団体会員拡大のための活動
⑤地域廃棄物適正処理推進議員連盟との連携強化ならびに支援強化のための活動
⑥会員の啓発ならびに広報のための活動総会終了後には新井貴志弁護士による「廃棄物の区分見直しと環境保全」と題する講演が行なわれ、17時からは別室にて懇親会が開かれた。地域廃棄物適正処理推進議員連盟会長の中川秀直衆議院議員、野田聖子衆議院議員、斉藤鉄夫衆議院議員らのあいさつ、環境省・経産省・農水省各幹部による祝辞が述べられたあと、西野あきら議員連盟副会長の発声により出席者一同高々と杯を上げ祝宴に入った。
総会の詳しい内容については「全清連ニュース」をご覧ください。
第三回定時社員総会開催 資料 <会員限定>
-

平成23年度の全国研修大会実施報告
続きを読む: 平成23年度の全国研修大会実施報告平成23年度「全国研修大会」を開催

一般社団法人全国清掃事業連合会(全清連)は10月26日(水)午後1時より東京千代田区の砂防会館を会場に、平成23年度の「全国研修大会」を開催した。全国から600名を超える会員が参集した本大会は、メインスローガンに「東日本被災地復興の取組みに連携し、地域環境の保全活動に邁進しよう!」を掲げた。被災地復興の現実の一端に触れて、復興支援連帯の今後のあり方について考え、また同時にその中で東日本大震災以降の我が国の社会経済状況下での我々固形一廃事業者の基本的方向を考える。第一部・全清連三井崇裕会長および議員連盟、各省庁のあいさつ、第二部・講演会、第三部・東日本大震災被災地無償活動報告と感謝状授与、当面の事業方針、大会決議、スローガン採択――の三部構成。環境省山本廃対課長および大震災で被災された岩手県大槌町からは(有)城山観光松橋専務による講演が行われた。全清連は環境省の要請に応じて東日本大震災被災地への無償支援活動を展開しており、第一陣ならびに第二陣の代表者が支援活動内容を報告するとともに、三井会長より感謝状が授与された。当面の事業方針は今回の場合、経団連や内閣府の規制・制度分科会がずっと提案している「廃棄物の定義・区分の変更」について、これは「どういうことか」を考える機会を提示するなど有意義な全国研修大会となった。
我々を押し潰そうとする規制緩和に対抗する理論武装を
全清連を代表して三井崇裕会長があいさつ。三井会長は冒頭、東日本大震災被災地への無償支援活動に際して、会員の方々から活動資金を拠出していただいたことへの感謝の言葉を述べた後、「私たちは何の目的でこのような研修大会を開催するでありましょうか」と研修会開催の目的について切り出した。「固形一廃収集運搬事業者である私どもを押し潰そうとする人たちがいる。いわゆる規制緩和です。廃掃法の定義・区分変更を要求する人たちです」「私たちの目的のひとつは、そういう人たちに対して、我々は正々堂々と対抗していかなくてはならない。手をこまねいているわけにはいかない」。こう述べ、そのためには「我々一人ひとりが理論武装しなくてはならない。この理論武装とは何か。後に詳しく触れますが、一緒に学習してきちんと理論武装してもらいたい」と強調した。
地域廃棄物適正処理推進議員連盟からは会長の中川秀直議員、副会長の西野あきら議員、石破茂議員、野田聖子議員ら衆参両議院から多数(16名)の国会議員が出席し祝辞が述べられ、環境省・伊藤哲夫廃・リ部長のほか経産省、農水省の幹部のあいさつが続いた。中川議連会長は東日本大震災に触れ、「大震災から生ずる生活環境の破壊、災害廃棄物に見られるような処理の困難さを思いますときに、あらためて生活環境をしっかり守っていくことの重要性の認識が高まったのではないか。皆さんが長い間、廃掃法の理念に基づいて生活環境の保全活動をされてきたことにあらためて敬意を表したい」と語った。講演、被災地・岩手県大槌町の現況
第二部の講演は、環境省山本昌宏廃対課長の「環境省の東日本大震災への対応について」と、東日本大震災の被災地から(有)城山観光の松橋明専務による「被災地・岩手県大槌町の現状について」。大震災で津波にのまれながらも九死に一生を得た松橋さんは当時の様子を振り返ると同時に被災者の現状を生々しく語る。大震災で東日本は人的、物的被害を受けた。松橋さんも親戚、友人、多くの仲間を失った。「先の見えない生活、絶望感……。動いていないと気が変になりそうだ。自分は仮設住宅の設置、物資の運搬と忙しく動き始めた。日が経つにつれ、仕事にも疲れを感じ、避難所生活のストレスの毎日」。そんなある日、「業界のバス会社社長から、全清連というボランティア団体が来るので面倒をみてやってくれ」といわれた。「何で俺が? 全清連って何? 復興に忙しい自分に何をしろというのか」。松橋さんの正直な感想だ。全清連到着の日、「トラックと人数にびっくり」。全清連のボランティア活動を見て、松橋さんは日増しに勇気づけられていく(詳しくは全清連ニュースをご参照ください)。
廃棄物の定義・区分の変更とはどういうことか
第三部は「東日本大震災被災地無償支援活動」の模様を第一陣救援隊隊長の片野理事、ならびに第二次救援隊副隊長の三井常任理事がそれぞれ報告。さらに無償支援活動に尽力した147名、ならびに運搬車両を無償提供した26社を代表して、中部、四国・近畿、九州・四国の各ブロックなどに対して三井会長より感謝状の授与が行なわれた。
このあと当面の事業方針を山田専務理事が説明。当面の事業方針は今回の場合、経団連や内閣府の規制・制度分科会がずっと提案している「廃棄物の定義・区分の変更」は、それは「どういうことか」について考える機会を提示した。平成10年、経団連を中心に生活系廃棄物処理の自由化を進めていくというテーマが出された。これに反対するために全清連という組織を立ち上げた。しかし生活系廃棄物処理の自由化の動きは今なお続いている。事業系一般廃棄物を産廃に付け替えようという動きが、内閣府の規制・制度分科会で出され、一廃・産廃の区分の見直しも俎上にあげられようとしている。規制が緩和され、廃棄物の定義・区分の変更が行われたら、固形一廃の業は立ち行かなくなる。倒産する会社が出る。死屍累々となるだろう。とくに東日本大震災という未曾有の災害が起きて、そのどさくさに紛れて復旧・復興をスムーズにするため規制緩和をしないといけないと言い出している。これは5年間続きますから。その間に、災害廃棄物だけでなく、一般廃棄物も見直したほうがいいんじゃないかということを言い出す可能性も十分ある。我々は注意深くその動きを見ていかなくてはならない。こうした一方で、平成20年に環境省から6.19通知が出された。全清連が10年をかけて勝ち得たものだ。しかし、この6.19通知は個々の会員が知識として知っているだけではだめだ。十分理解して、市町村や議員に説明し、相手が納得してくれるよう話すことができなければならない。全清連会員の個々のレベルを上げていかなくてはならない。勉強をして理論武装する必要がある。そうでないと自分たちの仕事は守れない。環境も保全できない。
研修大会はこのあと、大会決議、スローガン採択と続いた。
(研修大会の詳細は全清連ニュースに掲載)。 -

平成23年度の総会の報告
続きを読む: 平成23年度の総会の報告全清連・第二回定時社員総会開催
~役員改選を機に組織を拡充強化~
一昨年6月に一般社団法人となった全清連の第二回社員総会は5月17日(火)午後2時より大阪市のホテル日航大阪で開催。今回は東日本大震災の社会的影響の深刻さに配慮して規模を縮小して行った。任期満了に伴う役員改選では会長に三井崇裕氏(広島)の再任をとり決めたほか、副会長1名と理事5名を新任した。10年後の全清連の在り様を見据え、組織全体の本格的な充実強化を成し遂げるための新たな一歩を踏み出した。また総会に先立って、全清連がボランティア(無償支援活動)で行った東日本大震災の災害廃棄物撤去支援についての中間報告が発表された。
全清連の歴史に残る震災支援活動

総会では司会を岐阜県清掃事業協同組合の林和幸氏が努める中、まず三井会長があいさつ。三井会長は冒頭、「東日本大震災で被災された方々にお見舞い申し上げる次第です」と述べ、支援活動について環境省からの支援要請を受けて、4月27日~5月14日まで2週間強にわたり現地に支援に入ったこれまでの経緯を説明しつつ「各県から精鋭隊を現地に送り込んでいただき非常にすばらしい活動であったと私は見させていただきました。5月14日に全員で食事会をし、派遣された皆さんに感謝の意を伝えたのですが、皆さん涙ぐんで私の手を握り返してくれた方が沢山いました。何とも申し上げようがない感動の瞬間でありました。この活動を通じて我々全清連がいかに真摯に取組んできたかという証明になるのではないか。後世、全清連の歴史の一ページに残っていくものと確信しています」と評価した。 支援活動から帰還し、日を置かずして開催された総会だが、三井会長は「平成10年に任意ではありますがこの組織を立ち上げて、平成23年度は14年目に入る」としたうえで、平成10年に廃掃法の定義・区分の見直し問題が持ち上がり、「直営・委託・許可をやめて、自由化すべきだと。それが経済活性化につながるということが霞ヶ関で起きたわけであります。」と全清連設立の動機を語った。
環境保全の優先、変わらない基本スタンス
しかしながら「いまだ、民主党政権になっても皆さんご存知のように規制緩和が言われています」とし、全清連が結成以来、基本ベースとしてきたこととして次の3点を上げた。「第一は環境保全の優先」これなくして安心・安全の循環型社会は構築できないのであります。ここは何としても踏ん張っていかなくてはならない。ということは、「環境分野では規制強化が不可欠である。」これが2点目。そして3点目は私どもの固形一般廃棄物処理は市町村の自治事務でありまして、「我々は市町村の代行者であるという位置づけであります。」大きくこの3点が私どもの基本スタンスであると思っていますし、結成以来1日たりともこのベースは変わっていないとした。
さらに、規制改革により「定義・区分のところを持っていかれますと、全国でいま約2万1000社という我々の同業者がおりますが、どれだけの会社が存続できるでしょうか。80%は倒産するでしょう。そういうことでいいのでしょうか。このことは我々、永遠のテーマとして戦い続けていかなくてはならない。このことだけはお忘れなきようお願いいたします」と強調した。
このあと議長に新潟県一般廃棄物処理業者協議会の大月伸一理事を選出し議案審議。①第一号議案・平成22年度事業報告~④第四号議案・平成23年度収支予算案を満場一致で承認。第五号議案の任期満了に伴う役員改選では、会長に三井崇裕氏を再任したほか、副会長1名、理事5名を新任した。
総会終了後は別室にて食事会が開かれ、和気あいあいの歓談が繰り広げられた。役員改選を機に組織の充実強化を図る
今回の役員改選では、副会長1名、理事5名を新任した。これは10年後の一般社団法人全国清掃事業連合会の在り様を視野におき、組織全体の本格的な充実強化を成し遂げるための第一歩である。
新任の副会長および新任理事は次の通り(敬称略)。
▽新任副会長
野々村清(岐阜県清掃事業協同組合)
▽新任理事
岡 光義(福島県環境整備協同組合連合会)、
林 和幸(岐阜県清掃事業協同組合)、
橋本拓実(大阪府清掃事業連合会)、
三井弘樹(広島県清掃事業協同組合)、
長戸隆弘(福岡県清掃事業協同組合連合会)総会の詳しい内容については5月末発行の「全清連ニュース」をご覧ください。


第二回定時社員総会開催 資料 <会員限定>
-

東日本大震災
続きを読む: 東日本大震災東日本大震災〜岩手県大槌町に災害救援隊を派遣
ダンプ969台分のがれき等を撤去

平成23年3月11日に発生した東日本太平洋沖地震は、日本観測史上最大のマグニチュード9.0を記録し、東北地方を中心に甚大な被害をもたらした。また沿岸部は地震で引き起こされた大津波により壊滅状態に陥った。このような状況の中、(一社)全国清掃事業連合会は、地域の生活環境の保全、公衆衛生の確保・向上を使命として一般廃棄物の適正処理に従事している立場から、環境省災害廃棄物対策特別本部からの支援要請に直ちに応え、会員、各県連に支援体制構築を呼びかけた。
未曾有の災害を前に、国、県、市町村の連携にも混乱が生じ、実際の支援活動は4月以降にずれ込むこととなったが、全国の会員で組織された全清連の災害救援隊は4月28日〜5月14日まで岩手県の大槌町で活動を行った。市内の至る所に残されたガレキ、廃家財、粗大ごみ等、災害廃棄物の撤去を支援。約3週間で、持ち込みダンプによる運搬台数は延べ969台、運搬量は7752m3に達した。当初は不審の目で見られることもあったが、真摯な作業態度と熱意が通じ、被災者からは感謝の声が多く寄せられるようになった。5月11日には岩手県環境生活部や環境省自然環境局が激励に訪問。また地元マスコミの盛岡タイムスや岩手日報の注目を浴びるまでになった。28日から大槌町で活動開始

被災地での廃棄物処理状況は、どこも充実したレベルとは程遠く、多くの被災者が困窮している状態であった。特に大槌町では、市街地全域が壊滅状態に陥ったため、他の市町村と比べ復旧に遅れを生じていた。手付かずのガレキの山が町内の至る所に散乱しており、全清連は地元と連携しながら同町で災害支援を行うことに決定。一刻も早い支援が必要とされていたことから、翌週の4月27日には現地へ向かうことになった。
大槌町内では、被災者と協議の上で支援現場を決定。その後、車両15台を2〜3チームに分け、分担することとした。
また作業に当たっては、人力での作業、積み込みが困難な大型廃棄物があることも想定していた。そこでオペレーター付きユンボ3台を手配していたが、当日搬送されてきたユンボはいずれも0.5m3の中型クラス以上であった。市街地はゴミとガレキで埋め尽くされており、作業路の確保もままならない状況を考えると大きすぎて機動性・運用性に欠いている。広範囲にわたる震災の影響で、どの現場もユンボが不足、取り合いになっている状況では、大きさまで配慮して確保する余裕がなかったようである。さらに3台のユンボに対し、2名のオペレーターしか来ていないというハプニングまであった。
しかし地元の方に、中型重機が動けそうな現場を探して手配していただくことで作業を開始することができた。オペレーター不足は、全清連隊員の中に操作できる者が居たため事なきを得た。
一方、支援現場を協議する中で、被災者から不信感を露わにされる一幕もあった。地元避難所の被災住民代表から、第一声で「本当に無償支援ですか?」と聞かれたとのことである。話を聞くと、震災発生直後から今まで、ボランティアと称してNPOや政治関係団体とする団体から、活動後に請求書が送られてくる事件が多発しているというのだ。被災者は多くの支援を求めているが、このようなことでは不信感が先に来るのも仕方ないことである。
全清連という団体の方針・活動等を説明し、さらに地元被災者と同行していたことで信頼を得ることができたが、被災地支援を巡っては、行政の縦割りや業者の縄張り、利権などのほか、詐欺紛いの問題まで発生しているようだ。
その後は避難所で生活されている方々から、次々と支援を求める声があがってきた。全清連はその要請に基づき、家財道具の撤去や住宅地の道路に溜まっている粗大ごみ、家電、汚泥、木くず、プラスチック等の収集運搬を実施した。
また作業を手配していただいた地元の方は「私たちのためにここまでしてくれる団体は他に居ない。何とか応えたい」と個人所有のミニユンボを貸し出してくれたほか、その日の夜に釜石市まで走り、0.25m3のユンボを借りて来た。
しかしこうした活動への被災者の感謝とは裏腹に、ゼネコンの地元下請け業者などからは、非協力的な雰囲気が少なからず漂って来ていた。手配していた重機とオペレーターが無断で別の現場で作業していたり、ダンプ積み込み時の対応に配慮を欠いていたとのことである。
初日を終え、全清連のメンバーが宿泊地に戻った夜のミーティングでは、行政を無視した越権行為を行っていないか?ゼネコンの利権侵害と見なされていないか?といった不安から、今後の支援の方向性について議論が行われた。しかし利権・派閥といった問題はあるが、全清連の活動目的「環境保全の推進」「国民の安心・安全」に立ち返り、被災者が求め、対応が可能なことであれば何でもやるとの決意で一致団結した。
2日目以降は、神社、事業所、個人宅、住宅団地、保育園等と順々に活動。住民の方々から「まともなお礼もできませんが」としながらも、飴やジュースの差し入れと多くの感謝の言葉をいただいた。5月6日に第二陣へ作業引継ぎ

第一次派遣隊が段取りを済ませ、さらに4名の作業員が残ったために、第二次派遣隊のスタートは好調なものとなった。
第一次派遣隊と同様に盛岡市のホテルを午前6時半に出発、大槌町では5台の重機と手積みで作業を実施した。14日までに、地元建設会社の依頼で、花輪田地区と桜木地区の浸水家屋から家財道具を撤去。大ケロ地区でも途中までしか作業できないのを前提に、一部撤去。また津波が直撃した吉里吉里地区、山田町の水産会社関係、宮古市の水産会社関係から災害廃棄物の撤去を実施した。
宿泊地では、各ブロックごとに班長および副班長を決め、夕食後にミーティング。その日の反省報告と次の日の行程確認作業を実施。朝礼は班長・副班長がその日の抱負を述べ、隊員の士気を高めた。
また班長・副班長は作業中も的確な重機の移動、作業指示を行い、頼れる存在となっていた。数日も経つと、他のメンバーも「効率よく動くため」「少しでも復興に近づくため」という意識が働き、隊全体に良い効果をもたらしていた。
この頃から作業を手配いただいている地元の方から「全清連の活動が評判になっている。あっという間に片付く。凄い連中が来ている」と言われるようになって来ていた。4日に撤収、東梅副町長と面会

被災地からの撤収は、当初の予定通り14日。午前中で作業を打ち切り、大槌町の東梅政昭副町長へ挨拶に伺うこととなった。
東梅副町長からは「たまたま全清連が片付けてくれたところに、私の家もあった。あれだけのごみがあっという間に撤去されて、全清連の機動力に驚いた」と感謝が伝えられた。
また最後に14日間の作業の慰労と、地元で世話をしていただいた方々へ感謝を込めて慰労会を開催した。
出席した被災者は「20年以上かけて汗水流して築き上げたものが、一瞬にしてすべてを失った。茫然自失していたところに、全清連の皆さんが来てくれて、地元の人々も強者たちが来てくれたと喜んだ。たくさんの勇気をもらえたとともに、将来に向けて、負けてたまるか、という思いが込み上げてきた」との言葉をいただけた。H23.3.14 東北地方太平洋沖地震による災害廃棄物の処理支援への協力について 全清連より H23.3.14 平成23年東北地方太平洋沖地震により生じた災害廃棄物の処理への御協力について 環境省災害廃棄物対策特別本部 発出 H23.3.14 今後の支援へのメッセージ 議員連盟 会長 中川秀直衆議院議員 より H23.3.16 東北地方太平洋沖地震の被災地支援について№1 全清連より H23.3.17 東北地方太平洋沖地震の被災地支援について№2 全清連より H23.3.17 緊急理事会 開催のお知らせ 全清連より H23.3.17 計画停電実施時における節電について 環境省 廃棄物対策課 発出 H23.3.18 東北地方太平洋沖地震の被災地支援について№3 全清連より -

平成22年度の全国研修大会実施報告
続きを読む: 平成22年度の全国研修大会実施報告平成22年度「全国研修大会」を盛大に挙行

一般社団法人全国清掃事業連合会は10月22日(金)午後1時より東京千代田区の砂防会館を会場に、平成22年度の「全国研修大会」を盛大に挙行した。「環境保全優先、安心・安全の循環型社会を目指そう!」のメインスローガンのもと、全国から600名を超える会員が参集した。(財)日本環境衛生センター・三本木徹特別参与の基調講演ならびに地域活動の事例発表を通じて課題を認識し、問題の共有化を図った。
廃棄物の区分見直しの問題が依然としてくすぶっている。政府は行政刷新会議(議長・菅直人首相)の規制・制度改革分科会の民間委員トップに住友商事の岡素之会長の起用を内定、10月中に岡氏を含む新委員約15名を選び、本年度末をメドに医療、環境、農業分野などで規制の見直し案を策定するといわれている。区分見直しが論点として答申等に要求項目として記載され、環境省に対して中環審等での検討が求められるに至った場合には、全清連の論点をあらゆる機会を通じてあらゆる関係者(各政党、議連、有識者、環境省等々)に訴求することを事業方針とした。また、入札導入事案や新規許可乱発の増加などが顕在化している地方については、6.19重要事項通知の周知活動をなお一層の熱意と粘り強さをもって取組むことも方針として示した。会員一人ひとりが自らの「業」を守るためには全清連の組織強化を図ることが不可欠であるとの認識に立ち、会員加入促進の活動を展開することも求めた。我々の役割、使命は地域の環境保全の確保
全清連を代表して三井崇裕会長があいさつ。「我々の役割、使命は廃棄物処理法にあるように、地域の環境保全を確保する。これが我々の役割、使命ではないかと思うわけです」と切り出した三井会長は、「課せられた役割、使命のため我々の現場では業務品質向上を日々頑張っているわけですが、それにもかかわらず規模の経済、効率化という表現で廃棄物処理法の定義・区分の見直しが浮上してきている」とし、さらに入札問題や新規許可の乱発増加という現状について述べたあと、「(全国研修大会を通して)全清連会員は何が求められるのか、何をしなくてはならないのかを共有していきたい」と結んだ。
地域廃棄物適正処理推進議員連盟からは会長の中川秀直議員、副会長の西野あきら議員、石破茂議員、野田聖子議員ら衆参両議院から多数の国会議員が出席し祝辞が述べられ、環境省・伊藤哲夫廃・リ部長のほか経産省、農水省の幹部のあいさつが続いた。中川議連会長は環境省が平成20年6月19日に出した通達について触れ、「経済性の確保以上にしっかりした一般廃棄物の処理を市町村が責任をもって確実に行なうというのが重要であるという通達であったわけですが、能力のない人まで(ごみ処理を)やっていいとか、ただ安ければいいとか、そういうことになると本当に大きな問題が生まれてくる」と、市町村が清掃業務に入札などの経済合理性を導入することへの危惧を示した。また石破議員も「市町村は一年に大体どのくらいのごみが発生するのかわかる。ならばそれを超える業者をなぜ認めなければならないのか」と新規許可を出すことに疑問を呈した。講演、地域活動事例発表を糧に
講演は元厚生省(現・環境省)水道環境部環境整備課長を務め、いまは(財)日本環境衛生センターに籍をおく・三本木徹氏。「私の人生のほとんどが廃棄物処理の仕事に携わってきた」と自己紹介を兼ねてあいさつを述べる三本木氏の講演テーマは「ごみ処理事業の性格と規制緩和の問題点」。サブタイトルに「ごみ関係の規制のあり方を巡る近年の議論と、市町村とごみ処理業との役割に関する考察」という名称がつけられている。
このテーマの通り講演は、廃棄物の定義・区分、一般廃棄物処理業の許可要件の強化と手続きの簡素化・緩和――などについて歴史的経緯から説き起こし廃掃法の解釈ではどう捉えるべきかなど非常に示唆に富む解説だった。要点の一コマを紹介すると「廃棄物処理法という目的は、口をすっぱくして言いたいわけですが、適正な処理を進めるというのが基本であります。法律の目的でそこははっきりしてますね。公衆衛生対策であり環境保全であるというのははっきりしている。そこには経済合理性とか、そういうことは一切出てきません」(三本木氏の講演の詳細は全清連ニュースに掲載)。
「地域活動事例発表」は、「久留米市における一般競争入札の回避と今後の課題」(福岡県清掃事業協同組合連合会)、「三原市における新規許可問題への取組み」(広島県清掃事業協同組合)、「高槻市の入札問題について」(高槻市環境連絡協議会)の3件。事例発表で共通するのは「長年落ち度もなくやってきたのにある日突然に」ということだ。市町村合併を行った久留米市。合併前旧3町のごみ収集業務を約40年間随意契約で行なってきたものを、外部監査報告書により突然一般競争入札にすると市が通知。地元業者・福岡県清連・全清連が団結して市に粘り強く交渉。その結果、市側が入札を断念。また高槻市でも1969年(昭和41年)より随契でごみ処理をしていた業者が包括外部監査報告によって、2011年(平成23年)から競争入札にすると市から通知を受けた。決着はいまだついていない。三原市では突如新規許可が増加する事態に、組織を挙げて日参の交渉――など具体的な事例と対処方法が報告された。 このあと全清連としての当面の事業方針が述べられ、新規加入団体の紹介が行なわれるなど有意義な全国研修大会となった(詳細は全清連ニュースに掲載)。 -

平成22年度の総会の報告
続きを読む: 平成22年度の総会の報告全清連・第一回定時社員総会開催
~組織の進化と団結を~
昨年6月に一般社団法人となった全清連の第一回定時社員総会は4月21日(水)午後1時半より東京千代田区の「如水会館」を会場に、全国を代表とする社員22名および会員オブザーバー195名の出席を得て開催した。今総会では記念講演としてテレビや多数の著書の中で、市場原理至上主義に警鐘を鳴らしてきた経済評論家・内橋克人先生をお招きして、「市場原理至上主義を超えて」を演題にお話しいただいた。あらためて我々の仕事の意義・重要性、さらに全清連という組織の必要性についての認識を深めつつ、全清連は次の10年に向けて活動を開始した。
三井会長、「環境を守るため、全清連は強くならなければならない」
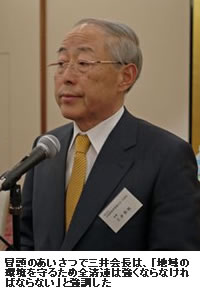
総会は川合副会長が出席人数を確認、定款に基づき総会が成立した旨の開会宣言のあと、三井会長があいさつ。三井会長は、地域の環境を我々の手で守り続けるためには、「この組織は不可欠であり、この組織は強くならなければならない。進化し、団結しなければならない」と強調した。
「私どもの全清連は何をするのが目的なのか」「どんな姿勢が我々にあるのだろうか」と切り出した三井会長は、環境保全の原点は我々の仕事にあると次のように述べる。
「私どもはそれぞれの地域で環境を守るために懸命に昼夜を問わず汗をかきながら頑張っている。地域の環境保全はきちっと私どもの手で運営し、きれいなまちづくりを推進してきております。このことが原点となってはじめて循環型社会の構築も可能でしょうし、さらに低炭素社会にも挑戦できるわけです」と、循環型社会、低炭素社会の原点は我々の仕事にあると指摘。
しかしこのような使命を全うしているにもかかわらず、「時の流れとともに規制緩和という時代に入ってきました。市町村によっては新規の許可を乱発してみたり、委託業務を入札化していく。なぜこういうことになるのか。現行の廃掃法の理念からしても、こういうことはあってはならないことになっているにもかかわらず。廃掃法をまったく無視してやっている。そういう首長さんたちに我々は何も言えないのか。私は決してそうではないと考えています」と述べ、このことは大きな課題であると位置づけ、「規制緩和、地方分権という名のもとに、とんでもない方向に押しやろうという勢力も出てくる。これを止めるためにも「全清連という組織が必要なのです」と呼びかけた。
最後に、「我々はこれから地域の環境を守り続けるという、若い次の世代に継承できるだけの財産を残していかなくてはならないのではないか。そのためにはこの組織は不可欠であります。皆のためにこの組織は強くならなければなりません。我々はこれから進化し、団結しなければならない」と訴えた。総会終了後の懇親会では来賓に地域廃棄物適正処理推進議員連盟会長である中川秀直議員、石破茂議員、野田聖子議員、竹本直一議員、山口俊一議員、岸田文雄議員、平井たくや議員、弘友和夫議員、浅野勝人議員、魚住裕一郎議員、塚田一郎議員、末松信介議員ら地域廃棄物適正処理推進議員連盟の国会議員を迎えあいさつが述べられ、環境省谷津廃・リ部長、農水省、経産省の関係省庁も出席しての歓談が続いた。
全清連平成22年度の事業計画
事業の基本方針は以下の4点。
①廃棄物・リサイクル制度に関する対策活動の推進
②地方における6.19通知に係る周知活動の推進
③全清連組織の拡充強化
④啓発活動の積極的推進経済評論家・内橋克人先生の特別講演
~市場原理至上主義を超えて~
約90分に及ぶ内橋先生の講演、話の中からはいくつかの『キーワード』をすくい取ることができる。「生きる・働く・暮らす」「社会的企業」「シンク・スモール・ファーストの社会が始まろうとしている」「行き続ける社会(持続可能な社会)」「グローバルズの行き詰まり」「社会的連帯感」「規制緩和・市場原理主義と歴史的検証」「努力した者が報われる社会を、というトリック」「官から民へが生んだ格差社会」。
「皆様方のお仕事を知れば知るほど、皆様方の力をやはりひとつに結集していくことがいかに大切か。現在の(社会)状況では全国的な大きな力になりうる集団をつくる。これが大変大事だと思います」。内橋先生は講演の口火をこのように切った。
以下、講演の一端を掲載する(続きは全清連会員のみ読むことが可能です)。第一回定時社員総会開催 資料 <会員限定>

活動報告
活動報告
activity