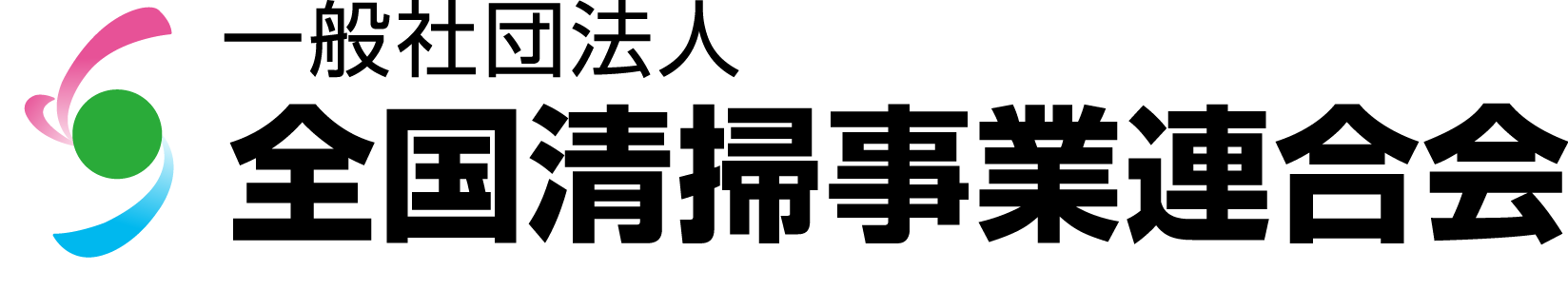-

西日本豪雨
続きを読む: 西日本豪雨全清連、環境省初期対応グループとして平成30年7月豪雨の被災地支援に出動
広島県全域で延べ31日間、1033名、566台展開

平30年6月28日から7月8日頃にかけ、西日本を中心に広い範囲で記録的な大雨が襲った。各地域で河川の氾濫や浸水災害、土砂災害等を引き起こし、後に「平成30年7月豪雨(西日本豪雨)」と命名される大災害へと発展した。全国で220名以上の犠牲者を出し、また広島、岡山、愛媛の3県だけで290万tと、平成28年熊本地震とほぼ等しい災害廃棄物が発生した。この様な状況で(一社)全国清掃事業連合会は、環境省の災害廃棄物処理支援ネットワーク(D.Waste—Net)の初期対応グループとして、被害が深刻な地域の一つで、いち早く支援要請が来た広島県三原市を中心に支援活動を展開。同県での活動期間は全域で延べ31日間、人員1033名、車両566台の規模に及び、被災地の災害廃棄物処理を支援した。

平成30年7月豪雨の被害が広がった要因は、6月29日に発生した台風7号、さらに同台風の影響を受け梅雨前線が停滞し、長期にわたり大雨が降り続いた影響が大きい。気象庁では7月6日、長崎県、福岡県、佐賀県、広島県、岡山県、鳥取県、京都府、兵庫県の順で大雨特別警報を発表。翌7日には岐阜県、8日には高知県と愛媛県、最終的に11府県に警報を発表した。
各地域では7日から河川の氾濫、土砂災害が生じ始め、電気、ガス、水道、道路など各種インフラが寸断。住宅被害は31道府県で48,470棟、さらに家屋損壊等により広島県で195万8,200t、愛媛県で52万9,539t、岡山県で41万2,900tもの災害廃棄物が発生した。
全清連の会員には、従業員や施設、車両に大きな被害はなく、発災直後からそれぞれの地元で災害廃棄物収集に取り組んだ。
岐阜県では、岐阜県清掃事業協同組合(岐清協)が岐阜県との「無償団体救援協定」に基づく要請を受け、10日付で同県関市においてダンプ2台、パッカー車1台、各2名乗車にて、7月12〜27日の期間で13日間の支援活動を実施。
また被害が大きい広島県では、(一社)広島県清掃事業連合会(広清連)との「災害時無償支援協定」に基づき、10日付で県から広清連に支援要請が寄せられた。これを受け三次市、府中町、海田町、坂町、世羅町、東広島市から要請があり、関係団体との連携のもと各地域で順次支援活動を展開した。
活動期間は、海田町で14日から延べ12日間、世羅町で10日から延べ12日間、東広島市で7月30日から随時、府中町で15・28日の2日間、坂町で16日から延べ9日間、また三次市は被災直後の9日から会員一社が活動していたが、10日から広清連の支援部隊が加わり延べ22日間、広島市も広島市廃棄物処理事業協同組合を通じ延べ21日間、支援部隊を派遣し、被災地の収集運搬や、仮置き場からの災害廃棄物転送を支援した。
一方、全容把握を進めていた環境省でも7月12日、全清連に対し廃棄物適正処理推進課長名で「平成30年7月豪雨により生じた災害廃棄物処理へのご協力について」とする支援要請を発出。これにより、全清連としても環境省の災害廃棄物処理支援ネットワーク(D.Waste—Net)の初期対応グループとして出動することが決まり、いち早く全清連に直接支援要請が出された広島県三原市へ向かうことになった。
第1次支援は7月16日から7日間、広清連、鳥取県清掃事業協同組合、山口県清掃事業連合会、さらに地元の三原市清掃事業協同組合の合同チームが、地域の災害廃棄物収集運搬に当たった。その後は一度、災害廃棄物の収集運搬を電話受付によるスポット対応に切り替えたが、被害の大きさから想定より多くの依頼が殺到。対応が困難と判断した三原市はさらなる支援を全清連に要請し、第2次支援として広清連、(一社)大阪府清掃事業連合会の合同チームが8月6日から5日間現地に入った。第一次、二次合わせ、延べ12日間、人員282名、車両138台の規模で被災地を支援した。
-

平成30年度の総会の報告
続きを読む: 平成30年度の総会の報告全清連・第九回定時社員総会開催
~結成20年の成果を糧に今後も適正処理を推進~

一般社団法人全国清掃事業連合会(全清連・三井崇裕会長)は、4月25日(水)午後2時より千代田区の如水会館を会場に、オブザーバーを含め総勢223名の出席を得て、第九回定時社員総会を開催した。全清連は結成からこの平成30年度でちょうど20年という節目の年を迎える。冒頭のあいさつで三井会長は結成時から今日に至る20年を振り返り、固形一般廃棄物に生起した様々な問題への対応や議員連盟の結成、環境省の6.19課長通知発出に続く10.8部長通知など、全清連が活動してきた努力の成果を述べ、今後も組織をしっかり固めて適正処理推進のために頑張っていきたいと強調した。また、総会終了後には講演が行われ、その後の懇親会では地域廃棄物適正処理推進議員連盟の石破茂会長をはじめとする多数の国会議員、関係省庁幹部らが出席しての祝宴が開かれた。 定刻通りはじまった定時社員総会は、開会に先立ち全清連の「連合会旗」が入場。全員起立し大きな拍手で迎えた。正面に掲げられた国旗ならびに連合会旗に向かって君が代を斉唱して総会は幕を開けた。大前清彦副会長 (大阪府清掃事業連合会)が開会宣言を行い、三井会長が全清連を代表してあいさつを述べる。
三井会長のあいさつ=この20年で大きな地位を勝ち取った=

平成10年に結成された全清連は、通常でいえば19回目の総会を迎え、平成30年度はちょうど結成20周年という節目の年を迎える。三井会長はこの20年間を振り返る。
「平成10年の結成には大きな理由がありました。7月26日の『日経新聞』朝刊のトップページに、固形一般廃棄物の直営委託許可を廃止すべきだと、そして自由業にすべきだという規制緩和委員会の意見が掲載された。これには本当にびっくりしました。同志の方も新聞を読まれていたらしくて、私たちは連絡を取りながら東京へ結集しました」。
全国から同業者約1000人が永田町の「憲政記念館」に集結した。総務庁の建物の中に規制緩和委員会の事務局が置かれていたことを知り、組織がない中で何とか形をつくって交渉に入った。こういう中で、当分留保するという結論を得て、最大の難関は免れることができた。「これはやはり、あの時に集結した約1000人の方の、組織がない中で集結いただいたその力、あるいは熱意が規制緩和委員会に通じたのではないかなと思っています」。全清連の原点だ。
それから急きょ組織をつくりあげていったわけだが、そうした中で現場では固形一廃に関する問題がいろいろ起こってくる。「そのたびに環境省へ行って交渉するのでありますが、なかなか前に進まない」。で、「議連をつくろうではないかということで、当時、岐阜県出身の武藤嘉文先生のところへ相談に行きましたところ、快く引き受けていただいたんです」。自民党に加えて公明党議員も議連に加盟することになり、今日では「衆議院49名、参議院21名、合計70名の先生方が加盟をしていただいています」。
全清連結成から10年を経た平成20年の6月19日、環境省から「課長通知(6.19通知)」が出された。「この中身については皆さん承知置きの通りと思いますが、これは非常に大きな、我々にとっては一大転換ともいえる課長通知であるんです」。それから6年後の平成26年1月28日には「最高裁判決」が下りた。この流れで同年10月8日に環境省「部長通知(10.8通知)」が発出された。「大げさに言うわけではありませんが、私たち全国の固形一般廃棄物を取り扱う業界にとっては、本当に大きな地位を勝ち取ったというふうに私どもは考えておるんです」。全国1718市町村の中には、新規許可を出したり、委託業務の入札を実施する市町村がまだ相当ある。「私たちはこのもの(6.19通知や最高裁判決、10.8通知)を持ち合わせておりますから、正々堂々と市町村と対峙しながら説明して、入札制度導入をやめていただくとか、どうして新規許可が必要なのかとか、理論武装ができているわけですから、そういうような行動展開をするのが全清連という組織であります」。
いつ、どこからこの業界を規制緩和しようということが起きるかわからない。「自分の身を守るというか、そういうことについてもこの3点セットが現在のところ非常に大きな私たちの武器になるというか、このような大きな仕事を私たちはやってきたということを、自信をもって皆さん方にあいさつできるということは、本当にうれしいわけでございます」。
また市町村の規制権限が及ばないブローカー問題に関しても環境省から昨年の3月21日、6月20日に通知が出されたが、「正直言って私は、まだ我々の立場は弱いと思っています。これもこのままじゃいかんので、環境省と協議しながら進めていかなければと考えています」。 20年間の間、様々な問題が現場で起きる。「そのたびに意見を集約して環境省へもの申すと、そして議連の方へもご相談申し上げるという、そういうかなり激しい活動をやってきました。おかげさまで何とか大きな仕事はやれました。これも皆さんの協力のおかげ、支援の賜物と思っているんです。これからも組織をしっかりと固めて、一歩一歩、我々の役目である適正処理の推進のために頑張っていきたいと思っています」。平成30年度の事業計画
このあと議長に大月伸一副会長(新潟県一般廃棄物処理業者協議会)を選出し議案を審議。第一号議案・平成29年度事業報告(案)~第四号議案・平成30年度収支予算(案)を満場一致で承認。
なお、平成30年度の事業計画(案)は山田久専務理事が説明に立ち、基本方針を踏まえたうえでの具体的な各々の事業活動として以下の10項目を示した。①全清連発足20周年記念事業
②廃棄物・リサイクル制度に関する対策活動
③青ナンバー問題に関する対策
④地方における10.8部長通知等の周知活動
⑤非常災害、大規模災害による生じる災害廃棄物の処理支援活動
⑥地域廃棄物適正処理推進議員連盟との連携強化ならびに支援強化の取組み
⑦組織の充実強化と会員加入促進の取組み
⑧会員の啓発ならびに広報活動、
⑨一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習会への取組み
⑩東南アジアをはじめとする発展途上国に清掃業務車両(パッカー車、トラック車など)を寄贈する取組み
記念講演:「社員の働くモチベーションを高め、地域で愛される会社をつくる」

総会後には、福島県福島市に本社を置く古紙リサイクル会社「㈱こんの」の紺野通昭社長による表題の講演が行われた。紺野社長は1967年生まれの3代目。先代からの事業承継、古参の社員との確執などを乗り越え、同社を地元を代表する優良企業に育てた。北海道や宮城県、埼玉、東京にも営業所がある。古紙リサイクルが本業だが、書店とカフェが2店舗あり、最近では今年4月に福島に大戸屋をオープンさせた。2月末決算で初めて年商50億円を超え、社員もグループ全体で205名にまでなった。人手不足が社会問題化している昨今にありながら同社は、「おかげさまで人手不足という経験がない」という。講演会では人手不足をテーマの一つとして、同社がこれまでやってきたことなどが披露された。
「一番大切なのは教育」「幸せと満足の違い」「毎年1日だけ全社員が福島に集結して開催される講演会と社員表彰式。市民や取引先も来ている」「年に何回か行う無記名の社員アンケート」「毎回の給与明細に社長のメッセージを入れて思いを伝える」「月次に上がる決算書、試算表を全社員に公開。すべて社員に情報公開する」「障害者の雇用。賃金は健常者と同じ」「90歳まで働ける職場づくり」……など様々な取り組みが語られた。なかでも「無記名の社員アンケート」の実施を紺野社長は勧める。会社に対するイメージとか、上司はどんな感じとか、社長の評価などが書かれる場合も。「少しでも社員と理解が共有できればいいなあと思います」(紺野社長)。
石破議連会長「業界の性格付けが法的に確立している」

このあと会場を移しての懇親会では全清連の地域廃棄物適正処理推進議員連盟会長を務める石破茂議員が駆けつけあいさつを述べたほか、竹本直一副会長、寺田稔事務局長ら多数の国会議員や省庁幹部の祝辞・あいさつが続いた。
石破議連会長はあいさつで、「20年になる(全清連の)歴史の中で、法の趣旨をきちんと踏まえましょうね、そして皆様の業界は――これは最高裁でもはっきりしておる話でありまして、業界の性格付けというものが法的にも確立をしておるところであります。が、何となく法を形がい化するような仲介業者の存在でありますとか、あるいは法を形がい化すると言っていいのかどうかわかりませんが、全国には1,718もの市町村がありますので、それぞれに対応が異なるということがあろうかと思います。私ども与党といたしまして、1,718ある市町村、もし仮に皆様方のお仕事の趣旨を取り違えて、あるいは規制緩和すればいいんだと、安ければいいんだというようなことがありますれば、どうぞ私どもにお申しつけをいただきたいというふうに思っているところであります」と全清連を支援していくことを強調した。 乾杯の発声は溝手顕正議員。「乾杯!」の威勢のよい掛け声とともに出席者一同杯を高く上げ、各テーブルを囲んでの祝宴に入った。
総会の詳しい内容については「全清連ニュース88号」をご覧ください。
-

平成29年度の全国研修大会実施報告
続きを読む: 平成29年度の全国研修大会実施報告平成29年度『全国研修大会』を開催
―進むべき道は廃棄物の適正処理の推進―一般社団法人全国清掃事業連合会(全清連・三井崇裕会長)は10月25日、東京千代田区の砂防会館において全国から600名を超える会員や多数の議員連盟国会議員、関係省庁幹部らの出席を得て、平成29年度「全国研修大会」を開催した。冒頭のあいさつで三井会長は、昨年の廃棄物処理法の定期見直しなどを含め我々を取り巻く情勢は変化してきており、問題が生起してくるであろうが「廃棄物の適正処理の推進、これを目指して、過去もそうでありましたが、これからもそれを目指してやる。進むべき道は一本です」と強調した。3日前に行われた衆議院選挙の余韻が冷めやらぬ中、駆けつけて頂いた地域廃棄物適正処理推進議員連盟会長の石破茂衆議院議員や議連の国会議員の方々のあいさつ、神戸大学大学院経済学研究科の石川雅紀教授によるダイコー事件の総括にする講演、全清連山田久専務による当面の事業方針の報告などがつづき、有意義な研修大会となった。

三井会長あいさつ
過去もそしてこれからも、廃棄物適正処理推進の道
全国研修大会は開会の辞に続き正面の国旗および全清連旗に向かい出席者全員で君が代を斉唱したあと、全清連を代表して三井会長が壇上に進みあいさつを述べる。
平成28年度に廃棄物処理法の定期見直しが行われ、今年6月に法改正が公布。公布されない部分は通知等により措置されたと述べた三井会長は、続けて「私たちを取り巻く情勢は刻々と変化してきております。直近では規制権限の及ばない第三者の問題がございまして、これは悩ましい問題ではありますけれども、これも3月21日、そして6月20日に通知を発出いただきました。ただ一方では、相手方のほうは、皆さんご存知のように違法ではないという解釈に立っておられるということで、この問題については私どもこれから非常にしんどい戦いがあるんではないかという風に予測されます。また、今日は神戸大学の石川先生の講演がございます。この講演もダイコー問題を捉えて、先生の考え方をおっしゃると思いますので、最後まで研修していただきたいと存じます」と一廃処理業界を巡る課題などについて触れた。そして最後に「これからますます我々を取り巻く問題が生起してくるでありましょうけれども、強い意識ですね、廃棄物の適正処理の推進――これを目指して、過去もそうでありましたが、これからもそのことを目指してやるしかございません。進むべき道は一本ですので、深くご理解を賜って、最後までお付き合いをお願いしたいと思います」と強調して締めくくると会場からは大きな拍手が湧き上がった。
石破議連会長あいさつ
ブローカー問題で、法の形骸化を懸念
続いて地域廃棄物適正処理推進議員連盟会長の石破茂衆議院議員が、議連を代表してあいさつ。「廃掃法という法律は法律の中でも難しい法律でありまして、ぱっと読んだだけでは何が書いてあるのかよくわからんというところがございます」と切り出した石破会長は、「ただ、趣旨としてあの法律は第6条、第7条というところがポイントであると私は理解をいたしておるところでございます」と市町村処理責任を指摘。しかし「法律はいま、会長からお話があのましたように、いろんな考え方が成り立ちますもので、いわゆるブローカーというものが、我々は違法ではないんだというのですが、ぎりぎり考えるといろんな議論があるんだと思いますが、たぶん、法の形骸化というのはこういうことを言うのだろうと思っております。そういうブローカーが暗躍することになりますと、廃掃法6条、7条の趣旨というのはまったく生きてこないことになります」と懸念を示した。
議連の国会議員のあいさつは、議連副会長の野田聖子議員、事務局長の寺田稔議員をはじめ山本幸三議員、岸田文雄議員、二乃湯智議員らを含め多数から祝辞が寄せられ、つづいて環境省、経産省、農水省幹部らのあいさつが述べられた。
講演・ダイコー事件の総括
排出事業者責任とは
休憩を挟み第2部は講演会、第3部は当面の事業方針についての説明が行われた。
神戸大学大学院経済学研究科の石川雅紀教授を講師に迎えて開かれた講演会のテーマは、「ダイコー事件の総括―そこで問われたことは何か?」。平成28年1月にカレーチェーンを全国展開するココ壱番屋(ココイチ・愛知県一宮市)が、産業廃棄物(冷凍ビーフカツ)の処理を産廃処理業者のダイコーに委託したが、処理されずに不正転売されたこの事件は世間を騒がせた。当時、マスコミの報道や社会の風潮は「壱番屋は被害者。対応は立派。わるいのは産廃処理業者だ」というものだった。これに対して石川教授は「壱番屋が真っ白だというのは何かおかしい。ひっかかる」と自身の受け止め方を語る。それは、汚染者支払いの原則(PPP)によれば、「自分の出した廃棄物がどうなっているのか、管理していないのは明らか」ということになり、ダイコー、みのりフーズと並んで、ココ壱番屋も汚染者であるという結論に達する――。石川教授はこの事件をきっかけに、排出者責任とはどういうことなのか、論を展開する。当面の事業方針
環境省発出の7本の通知の理解を深めよ
第3部では「当面の事業方針」が山田久専務理事より説明された。
環境省はこれまで、一般廃棄物の適正処理推進に関して7本の通知を発出している。山田専務はこの7本の通知を改めて整理し、その重要性を説明した。発出された7本の通知はリンクしており、ひとつの「かたまり」となっている。一廃処理業者は理解を深め熟知しておく必要がある。たとえば、「6.19通知」(平成20年6月19日付)と「10.8通知」(平成26年10月8日付)は、ワンセットになっている。6.19通知が発出された平成20年の時代背景を山田専務はこう説明する。「平成5年からバブルが崩壊した。失われた20年ともいわれている。景気はデフレになった。そうするとどういうことが起きたかというと、規制緩和です。要するに規制を撤廃せよと。そうすることによって経済活動が活発化すると。だから市町村もどんどん許可を出し、入札、入札となった」。その時に6.19通知が出た。「一般廃棄物処理業の分野に規制緩和が押し寄せたときに、環境保全の重要性ということが一番最初に書いてある。当時は環境保全の重要性ではなく、経済合理性を優先するという社会なんです。市町村も何から何まで入札すればいいと。議会から責められますからね」。それだけに6.19通知の意義は大きい。
しかしながら通知が出て、自分たちが許可乱発や入札をしている市町村は、こういう状態をまずいなと思いながらも、議会にどう説明していいかわからない。「だから流れがなかなか変わらなかったんです。そして三井会長をはじめ、全清連の方々がこれだけではだめなんだと。環境省が出してくれた通知は今の規制緩和の流れを止めたけれど、止めただけで市町村は変わらない。何とか実効性ある措置を」となって、10.8通知が発出された。この10.8通知には、1月に出された最高裁判決の趣旨というところがある。ここが通知の一番重要なところ。「それを読みますと、平成26年1月28日の最高裁判決は、廃棄物処理法において一般廃棄物処理業は専ら自由競争に委ねられる性格の事業とは位置づけられないと言えるとしており」となっている。「最高裁の判決を引用して環境省の通知に出たということ。これが非常に大きいんです」「議会の先生が入札にせよとか、許可をどんどん出せとかやるわけです。それに対して10.8通知を読んでください。こういうのが国から出ていますよ。最高裁の判決ですよというと、市議会や県議会の先生は黙ってしまう。そういう内容なんですね」。
また、「8.30通知」(平成11年8月30日付)は、「ブローカー問題を取り上げた始まりだったが平成28年ぐらいまでの15年ぐらいの間にぐちゃぐちゃになってしまった」。ブローカー問題が深くなり、ダイコー事件が起きた。それがために排出事業者責任の徹底を示した「3.21通知」(平成29年3月21日付)が出て、「6.20通知」(平成29年6月20日付)であるチェックリストにつながっていく。
さらに「3.19通知」(平成24年3月19日付)は、「使用済み家電の不用品回収業者対策」であり、「1.20通知」(平成28年1月20日付)の「許可なく一般廃棄物が収集運搬された事案について」とは、同志社大学で同大学の子会社が一般廃棄物を無断で自己処理と称して、自己搬入といってやっていたものを摘発した事件。「いずれも無許可業者です」。
「無許可業者、ブローカー対策……。いまここにおられる皆さんが日常的に深くかかわっている問題なんです。どうかこの7本の通知を暗記するぐらい勉強して、行政の方ときちんと打ち合わせをしていただきたい」。最後に山田専務はこう締めくくって説明を終えた。
研修大会はこのあと大会決議、スローガン採択とつづき、最後は恒例となった「ガンバロー・コール」で滞りなく終了した。

(研修大会の詳細は、11月下旬発行予定の全清連ニュースに掲載)。 -

平成29年度の総会の報告
続きを読む: 平成29年度の総会の報告全清連・第八回定時社員総会開催
~会長に三井崇裕氏を再任~
一般社団法人全国清掃事業連合会(全清連)は、4月26日(水)午後2時より千代田区の如水会館を会場に、オブザーバーを含め総勢230名の出席を得て、第八回定時社員総会を開催した。今総会では任期満了に伴う役員改選が行われ、会長に三井崇裕氏の再任をとり決めた。総会終了後には(公社)大阪府産業廃棄物協会の龍野事務局次長による講演が行われ、席を移しての懇親会では地域廃棄物適正処理推進議員連盟の石破茂会長らをはじめとする多数の国会議員、関係省庁幹部らが出席して和気あいあいの祝宴が開かれた。 定刻通りはじまった定時社員総会は、開会に先立ち全清連の「連合会旗」が入場。全員起立し大きな拍手で迎えた。正面に掲げられた国旗ならびに連合会旗に向かって一同君が代を斉唱して総会は幕を開けた。野々村清会長代行(岐阜県清掃事業協同組合理事長)が開会宣言を行い、全清連を代表して三井会長があいさつを述べる。
三井会長あいさつ

この1年を振り返ると平成28年度は早々に生じた熊本地震への支援要請を筆頭に、大きな事業がいくつもあったと三井会長は述懐する。熊本地震においては環境省からの支援要請を受けて、「しっかり準備して熊本に入りました。約19日間、機材は520数台、投入した人材は1000名にのぼるという実に大きなものでした。おかげさまで後に環境大臣、熊本市長、益城町町長から全清連に感謝状が授与されました。皆様方、忙しい中を多くの方々が現地に駆け参じまして、市民のライフラインがキープできました。本当にありがとうございます」と出席者にお礼を述べた。6年前の東日本大震災に際しても環境省から支援要請があり、「組織を上げて全力を上げて現地に入り奮闘してまいりました。この実績が大きな反響を呼びまして、災害廃棄物をどうするかということを環境省も取り上げD.Waste-Netという組織をつくり、私どももそこへ登録することになりました」と説明。
28年度はこのほか、「廃棄物処理法の見直し」「食品リサイクル法の見直し」「容リ法の見直し」などがあったが、こうした中で「皆様にお約束した事業方針がありました。それは最近、全国各地にいるといわれております、仲介ブローカーと言っておりますが、文言的には『第三者』という表現になっております。これを28年度中に何とかきちんとしたいと皆様にお約束した。これも執行部体制の中で頑張っていただきまして、この3月21日付けでこの問題について環境省の方から『こうあるべきだ』というのが出てまいりました。私どもも少しは胸を張ってやり遂げた、という気分があります。今後皆様に大いに活用していただきたいということを申し上げたい」と述べ、続けて「廃掃法の見直し、食品リサイクル法の見直し、容リ法の見直し、そして第三者と言われる仲介ブローカー問題等、これらに私ども取り組んできたわけですが、結果は全部私どもの意見を重んじていただけたということになりました。今日お越しいただいた皆様と一緒に、少しは心休まる瞬間ではないかなと思っている次第です」と心境を語った。そして29年度についても「情報収集をきちっとして、環境保全を前提とした適正処理の推進により、地域のために頑張っていかなければいかんなと覚悟しているところです」と強調した。
平成29年度の事業計画と役員改選
このあと議長に大月伸一副会長(新潟県一般廃棄物処理業者協議会会長)を選出し議案を審議。第一号議案・平成28年度事業報告(案)?第四号議案・平成29年度収支予算(案)を満場一致で承認。第五号議案の任期満了に伴う役員改選では執行理事が選出されたのち、別室にて第1回理事会が開かれ協議。その結果、会長に三井崇裕氏の再任を取り決めたほか、執行部役員全員留任となった。
再任された三井会長は就任のあいさつで「環境保全を前提とした適正処理の推進は私たちの使命です。これを中心にして、問題が降りかかろうともきちっとした対応をすれば、法の目的、制度の目的に向かい邁進できるということは確信をもって言えますし、この18年間やってまいりました。これからも皆様と力を合わせて難関を乗り越えていきたい。私たちにしかできない仕事が沢山ありますので、自信をもって進めていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします」と述べると、会場から大きな拍手が湧き上がった。
なお、平成29年度の事業計画は山田久専務理事が説明に立ち、基本方針を踏まえた形で具体的には以下の8つを示した。
①廃棄物・リサイクル制度に関する対策活動
②地方における10.8部長通知等の周知活動
③非常災害、大規模災害による生じる災害廃棄物の処理支援活動の取組み
④地域廃棄物適正処理推進議員連盟との連携強化ならびに支援強化の取組み
⑤組織の充実強化と会員加入促進の取組みについて
⑥会員の啓発ならびに広報活動
⑦一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習会への取組み
⑧東南アジアをはじめとする発展途上国に清掃業務車両(パッカー車、トラック車など)を寄贈する取組み
新役員執行部 
就任挨拶をする三井会長 記念講演:「今、求められる廃棄物処理業の在り方」
総会後には、(公社)大阪府産業廃棄物協会事務次長の龍野浩一氏による表題の講演が行われた。龍野氏の講演内容は、①廃棄食品の不正転売事件から改めて確認できたこと。②最近の改正動向や解釈の明確化に関する相談内容と反応。③今、求められる廃棄物処理業の在り方=「総合環境事業」として……。の3点が柱。とくに③がメインになる。廃棄物処理業を取り巻く経営環境は、人口の減少や生産拠点等の海外移転などにより廃棄物が減少している。こうした中で処理業は2極化していくという。ひとつは「新しいビジネスモデルの模索」と「異業種の参入」。もうひとつは「許可さえあれば何とかなる。今の仕事が維持できればいい」というものだ。
そして、求められる廃棄物処理業の在り方としては、「循環型社会」「自然共生社会」「低炭素社会」「安全が確保される社会」といった、従来の枠組みを超えたビジネスモデルの構築が必要と指摘。これを地域に根差した「総合的なインフラ」としてシステム化していくことが重要とする絵柄を示した。石破議連会長からも熊本地震への支援要請

このあと会場を移しての懇親会では全清連の地域廃棄物適正処理推進議員連盟会長をつとめる石破茂議員が駆けつけあいさつを述べたほか、竹本直一副会長、斉藤鉄夫幹事長ら多数の国会議員や省庁幹部の祝辞・あいさつが続いた。
石破議連会長は「昨年の熊本震災につきましては、皆様に大変ご支援をいただき大勢の人々が助かったと思っています。国土はきちんと守りますが、皆様一人一人が健康で文化的、快適な暮らしができますように、全清連の皆様と力を合わせてやっていきたいと思います。
」と述べた。
乾杯の発声は寺田稔議連事務局長。威勢のよい掛け声とともに出席者一同杯を高く上げ、各テーブルを囲んでの和気あいあいの祝宴に入った。
総会の詳しい内容については「全清連ニュース85号」をご覧ください。
-

平成28年度の全国研修大会実施報告
続きを読む: 平成28年度の全国研修大会実施報告平成28年度『全国研修大会』を開催
―環境の保全に向け突き進む―一般社団法人全国清掃事業連合会(全清連・三井崇裕会長)は10月19日、東京千代田区の砂防会館において全国から600名を超える会員や多数の議員連盟国会議員、関係省幹部らの参集を得て、平成28年度「全国研修大会」を開催した。全清連の活動は廃棄物処理法の下、環境を保全することにある。冒頭のあいさつで三井会長は「環境の保全のために何ができるか。ご提案申し上げながら突き進んでいきたい」と強調。研修大会は環境省の講演、当面の事業方針などが報告された。

三井会長あいさつ 全清連の活動は環境の保全に帰する


全国研修大会は開催に先立ち、熊本地震で犠牲になられた方々に全員で黙とうを捧げた。開会の辞に続き正面の国旗および全清連旗に向かい君が代を斉唱したあと、全清連を代表して三井会長が壇上に進みあいさつ。
三井会長は、全清連が環境省の要請に従い4月末から19日間、熊本地震の災害廃棄物処理支援活動を展開したことに対して、一昨日の10月17日に山本公一環境大臣から感謝状を拝領したことを報告。その感謝状を披露し、会場を埋めつくした会員に向かって「ご協力いただきありがとうございました」と感謝を述べると、会場は大きな拍手に包まれた。
「全清連の活動は廃棄物処理法にあります環境の保全、これをいかに守るのかに帰するのでありまして、そうでなければ安心安全のライフラインがキープできない。そのために平成10年、規制緩和の嵐が吹き荒れる中、(全清連を)結成させていただきました」と述べた。全清連設立から18年を迎えるがこの間、「議員連盟を結成していただき、様々の問題が生起するたびに議連や関係省庁にも相談に乗ってもらい問題解決に努めてきた」と語った。
廃掃法の定期見直し、廃棄物管理会社の問題、食リ法の見直し、容リ法の問題などについて触れたあと最後に、「これからも皆さんのお力添えをいただきながら、環境保全のために私どもは何ができるのか、ということについてご提案申し上げながら我々は突き進んでいく覚悟であります」と強調して締めくくった。
続いて地域廃棄物適正処理推進議員連盟幹事長の斉藤鉄夫議員が、議連を代表してあいさつ。石破茂会長や野田聖子副会長が国会開会中、公務のため出席がかなわず、あいさつができなかったことをお詫びした後、「廃掃法を徹底させるための6.19又は10.8通知、これは最高裁がここはゆるがせにしてはいけないと決めたものであります。どうか皆様、自信をもって通知の徹底を行い、間違った行政に対しては意見具申をしていただきたい」とした。
このあと、熊本地震の災害廃棄物処理支援活動をされた430名の支援活動者、車両を提供した94社のそれぞれのブロックの代表者に対して三井会長から感謝状が授与された。
議員連盟、環境省、経産省、農水省幹部のあいさつが述べられたあと、休憩を挟み第2部として環境省廃・リ対策部廃対課の松崎課長補佐と産廃課の相沢課長補佐による講演が行われ、その後の第3部では「当面の事業方針」が山田専務理事より報告された。
当面の事業方針 環境省通知の学習と周知活動を
当面の事業方針について山田専務は、6.19と10.8通知の今後の周知活動の進め方について丁寧に説明する。
「10.8部長通知が発出して2年が経過する。少し振り返ってみたい」と述べ言葉を続けた。団体幹部役員は市町村に対して通知の周知徹底を求めるという前に、役員全員が通知の全文や主管課長会議等の読み合わせを行い勉強し、理解徹底に努めたのかと問いかける。
個人ではなく団体で「最高裁判決文から環境省が抜粋した部分については、一般廃棄物処理業とは何か、という根本的な問いに対する正確な答えが示されている」とし、「このことを徹底して理解しなければならない」。そのためには、個人ではなく「団体としての組織的な学習活動」が必要で、とくに「会員企業の幹部社員への教育として、6.19通知、10.8通知の全文学習を行うことが必要」と指摘した。
このほか廃棄物処理法見直しに対してはブローカー問題の対応を国に求めていることや、さらにD.Waste-Netへの登録については、大手事業者中心の体制になっていることへの違和感があること、全清連が自ら努力すべき課題としてエコアクション21の認証取得、業務品質向上マニュアル、BCPなどの取組みは必須であると強調した。
研修大会はこのあと大会決議、スローガン採択とつづき、最後は恒例となった「ガンバロー・コール」で幕を閉じた。
(研修大会の詳細は、11月下旬発行予定の全清連ニュースに掲載)。 -

平成28年度の総会の報告
続きを読む: 平成28年度の総会の報告全清連・第七回定時社員総会開催
~熊本地震の災害廃棄物処理支援に動く~
一般社団法人全国清掃事業連合会(全清連・三井崇裕会長)は4月27日(水)千代田区の如水会館において第七回定時社員総会を開催した。4月14日に発生した熊本地震。現地では震災によるごみ処理が急迫した課題となっており、全清連に熊本市や環境省から支援の要請が届いている。これを受けて本総会では急きょ平成28年度事業計画に災害廃棄物の処理支援活動という「熊本地震に対する支援の取組み」を上程、満場一致で可決承認された。総会終了後には明治大学大学院法学研究科の新美育文教授による環境省廃・リ部長通知と最高裁判決についての記念講演が行われ、また席を移しての懇親会には地域廃棄物適正処理推進議員連盟の石破茂会長らをはじめとする多数の国会議員、関係省幹部らが出席しての祝宴が開かれた。
午後1時半からはじまった定時社員総会は出席者全員、熊本地震の犠牲者に黙とうを捧げたあと、全清連の「連合会旗」が入場。大きな拍手で迎えた。正面には国旗ならびに全清連の連合会旗が掲げられている。これに向かって一同君が代を斉唱して総会は幕を開けた。
「全国の代表総数21名(委任状1通)とオブザーバー217名含めて総勢239名の出席です。これは定款第17条の総会成立要件を満たしております。本総会は廃棄物処理法見直しの年であり、我々の業界にとって重要な事業計画を慎重に審議する場所となります」と野々村会長代行(岐阜県清掃事業協同組合会長)が総会成立を宣言した。三井会長あいさつ

全清連を代表して三井会長があいさつ。「ただいまの野々村会長代行の開会宣言にありましたように廃掃法の見直しが迫っておりまして今年度から環境省が作業に入ると思います。またいろいろな問題が生起するでありましょうが、しっかりした足取りで対応してまいりたいと思っています」。三井会長は冒頭、廃掃法の見直しについて触れ、続いて本総会に初めて出席する会員もいることから、全清連の発足から今日に至る18年間の足取りをかいつまんで説明した。平成10年に全清連は発足した。「結成のときは経団連が規制改革委員会において、私どもがやっている固形一般廃棄物の直営、委託、許可の業を全部自由業にすべきだということを俎上してきたわけです。当時の事務局は総務庁でした。そこへ我々押しかけて行って、『これはどういうことなんだ』ということから始まりまして……。残念ながらその当時は固形一般廃棄物の全国組織がなかったんですよ。まったくなかった。そこから立ち上げて、皆さんの参加、努力のおかげでようやくこの18年間をクリアしてきたわけです。その問題は本当に心血注いで何とか防ぎました」と振り返った。
このあと、平成20年の6.19課長通知、平成26年の10.8部長通知、また最高裁判決が出された。「このことにおいて私どもの固形一般廃棄物の基礎をつくっていただいた。皆さんが頑張ったからであります」。ただし10.8通知が出たが、「我々は問題解決のために行動を起こさないと絵に描いた餅になる危険性があるわけです」とし、いまだ新規許可を出す市町村の首長がいるなど「10.8通知、最高裁判決からするとあってはならない案件に対して、私どもが首長に対して改善方を要請していく、そういう努力をしていかなくてはならない。それで私どもは地域ごとに全国研修会を毎年開催して、講師を招いてあるいは地元自治体に出席していただいて、廃掃法の制度とはどういうものなのかといったところを説明すると同時に、そうでない市町村に対しては改善していただく。そのことを一生懸命やっている途上であります」と全清連の取組みについて述べた。
最後に熊本地震への支援活動について、「一日も早く来てほしいというのが熊本市の要請でした。環境省からも部長名でぜひ支援してもらいたい旨の文書が届いております。それを受けて私どもは一刻も早く体制を組んで現地に入って支援活動を行っていきたい。一刻も早く廃棄物の除去のお手伝いをしたいと考えております」と強調した。平成28年度の事業計画
このあと議長に大月伸一副理事長(新潟県一般廃棄物処理業者協議会会長)を選出し、山田専務理事が説明に立って議案を審議。第一号議案・平成27年度事業報告~第五号議案・役員の選任を満場一致で承認したが、平成28年度事業計画については、「熊本地震に対する取組み」を急きょ上程し承認を求めた。支援のスケジュールを山田専務が説明する。4月30日に地震帯から外れている熊本県清掃協議会の天草と山鹿地区のメンバーが7台のパッカー車を出して5月2日まで支援します。そして5月3日からは鳥取、広島、山口、福岡のメンバー車両30台人員60名の体制で入る。今回は緊急ということで、熊本市が用意してくれたクリーンセンター会議室に貸布団を持ってきて泊まります。ただしスペースの関係で40名分しか泊まれない。なので福岡の皆さんには我慢してもらって日帰りで、毎日ピストンでやっていただくことになります。またこれらに係る費用、車両保険や損害保険、食料費用等々に関しては連合会の繰越予算の中から充当します――総会ではこれらの支援活動を承認した。
なお、平成28年度の事業計画活動方針は、基本方針を踏まえた形で具体的には以下の10項目を示した。
①基本方針
②廃棄物・リサイクル制度に関する対策活動
③地方における10.8通知の周知活動を通した地域の生活環境保全、公衆衛生確保向上のための取組み
④全清連の組織充実強化と団体会員拡大のための活動
⑤地域廃棄物適正処理推進議員連盟との連携強化ならびに支援強化のための活動
⑥会員の啓発ならびに広報のための活動
⑦D.Waste-Netへの参画に向けた取り組み
⑧一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習会への取組み
⑨東南アジアをはじめとする発展途上国に清掃業務車両(パッカー車、トラック車など)を寄贈する取組み
⑩熊本地震に対する取組み石破議連会長からも熊本地震への支援要請

総会終了後には明治大学大学院の新美教授による記念講演が行なわれた(別掲)。このあと会場を移しての懇親会では全清連の地域廃棄物適正処理推進議員連盟会長をつとめる石破茂地方創生担当大臣が駆けつけあいさつを述べたほか、野田聖子副会長、竹本直一副会長、斉藤鉄夫幹事長、寺田稔事務局長ら錚々たる国会議員や省庁幹部の祝辞・あいさつが続いた。石破議連会長は熊本地震に触れて「現地において、ごみの処理をどうしようかと困っておられる。全清連の方のお力をお借りしたい。お願いします」と支援を要請し、地震や津波の災害の歴史を語った。地域創生ということでは「地域地域で頑張っている方々、そこにきちんとしたいい仕事があり、ふさわしい収入があり産業が栄える。そういう意味で皆様方にお世話になることはこれから先、増えることはあっても減ることはないと思っております」と結んだ。
このあと南川秀樹特別顧問の発声により乾杯。和気あいあいの祝宴が繰り広げられた。全清連第七回定時社員総会 記念講演
明治大学大学院法学研究科・新美育文教授

新美教授の講演テーマは「廃掃法の適正な運用の徹底に係る環境省廃・リ部長通知と最高裁判決」というもの。平成20年の環境省6.19課長通知、平成26年の10.8部長通知、それに平成19年11月30日の東京地裁判決と平成26年1月28日の最高裁判決という一連の流れから、そこに示されている一般廃棄物に関する基本的な考え方を、環境法の研究家の立場から解説した。以下は講演要旨。
平成26年10.8通知の前に平成20年6.19通知がある。「これが本来、一般廃棄物に関する基本的な考え方が示されている」(新美教授)わけで、「そのまま素直に決定されたのならよかったのですが紆余曲折があり、最高裁に諍いが持ち込まれた。そしてその決定を受けて10.8通知になった」。
6.19通知発出には前提があったと新美教授は語る。それは平成19年11月30日の東京地裁の判決が6.19通知のベースになっていると指摘する。東京地裁で判決が出された訴訟とは簡単に言うと、一部の住民が、武蔵村山市が平成16年、平成18年の各年に締結したごみ収集運搬業務委託契約は、地方自治法第234条2項に違反する随意契約であると主張し、住民監査請求を起こし損害賠償金の支払い請求を求めた事案。要するに随契で行ったことは一般競争入札ではないから違法だという主張だ。これについて東京地裁は住民の訴えを退けた。その理由について長々と述べているが要諦としては『価格の低廉性を重要な要素と位置付ける一般競争入札によっては、その趣旨の実現を図ることは困難である』ということ。その趣旨の実現とは、廃棄物処理法による一般廃棄物の適正な処理は、住民が衛生的な環境下において健康で文化的な生活を営むことを指す。
こうした諍いがたびたびあったので、廃掃法の趣旨をより徹底するということから6.19通知が出されたわけだが、それでも「首長さんの中には廃掃法の趣旨が十分理解できていなくて、一般競争入札に流れることもないわけではない。一般競争入札の問題については6.19通知ではっきり出されたが、実はちがう諍いも出てきたわけです。随契でやるというのは、首長が自分の裁量でやっていいのかという問題です。この問題が現れたのが最高裁の平成26年1月28日判決であり、それを踏まえて平成26年10.8部長通知が発せられているわけです」。
最高裁も平成19年の東京地裁の考えを確認している。「一般廃棄物処理業はもっぱら自由競争に委ねられるべき性格の事業とは位置づけられていない。許可要件に関する市町村長の判断にあたっては、区域における一般廃棄物処理業の適正な運営が継続的かつ安定的に確保されるように、地域内の需給の均衡とその変動による既存の許可業者の事業への影響を適切に考慮することが求められる」と最高裁は考え方を述べている。
要するに「首長は処理計画がきちんと行われるように施策を講じていかなければならない。そのための処理業者選定については、経営基盤や技術などいろいろなものを考慮する必要がある。自由裁量ではない。現在の許可業者は他の処理業者に対してなされた許可に対して利害関係を持っている。処理計画にきちんと配慮した、実現するための許可なのか、ということについて訴えあるいは異議を述べることができると最高裁は言っているわけです」。そういったことからも改めて市町村の一般廃棄物処理責任の性格を通知した「10.8部長通知は熟知完読しておく必要がある」。総会の詳しい内容については「全清連ニュース79号」をご覧ください。
-

熊本地震
続きを読む: 熊本地震熊本地震の震災廃棄物
全清連、処理支援に向かう

4月14日に震度7の地震が発生し、その28時間後の16日にも震度7の地震に見舞われた「熊本地震」。現地では発災当初、食料・水・トイレ・住居などの確保難に陥ったが、それと同時に地震によって発生した震災廃棄物の処理に困り果てていた。環境省から全清連に支援準備の要請が入る。熊本市からは支援要請が届いた。これを受けて全清連は急きょ体制を組み、余震が続く熊本市に向かった。
支援要請を受けて動ける
ごみ処理に困っているところには本来、要請があろうがなかろうが支援に駆けつけるのが筋といえる。しかし今回のような震災廃棄物の処理支援になると相手の要請がなければ動けない。というのもこのような場合、現地は混乱を極めており、それを考慮しないで支援に行ったらさらに混乱に輪をかけ、現地の人たちにかえって迷惑をかけることにもなりかねないからだ。
全清連の支援体制は各県連から、支援が可能な車両、人員を出してもらい活動にあたるというもので、熊本県、大分県、福岡県、中・四国協議会(山口県、広島県、鳥取県、高松)の各県連から支援が出た。支援活動期間は各県連の事情によって多少の違いはあるが、ゴールデンウイークの4月30日?5月9日、5月14日、15日の12日間。パッカー車、ダンプ車、アームロール車等、延べにして車両台数347台、作業人員は717名という規模。復旧支援で被災地に少しでも貢献を
5月3日午前7時。焼却施設である熊本市東部環境工場近くの「ふれあい公園」で、支援活動の人員が集合し激励会が行われた。激励会では三井会長と熊本市の川口環境部長があいさつ。
三井会長は「本日は中四国ブロックから香川県、鳥取県、山口県、広島県、九州ブロックから福岡が参加しております。まず厚く御礼申し上げます。大変な災害です。まだ余震も続いています。どうか十分気を付けて、怪我などないよう、事故のないように一生懸命頑張っていただきたい」
「私たちはちょうど5年前、東日本震災で現地に赴き、このような活動をさせていただいた。まさか同じ時期にこうしたことが起こるとは想像もしていなかったわけですが…。皆さまは、特に現場はスペシャリストであります。東日本大震災でも評価を受けたが、今こそこの復興に対して復旧作業に入るわけですが、被災地に少しでも貢献できるよう尽力したいと思いますので、どうかご協力をよろしくお願いします」と述べた。応援隊は復興のきっかけ。頑張る気持ちにもなる
熊本市の川口環境部長は「先日の14日に震度7の地震、その2日後に震度7がもう一度あり、それがかなり致命的でした。熊本市東部の方面でもかなりの倒壊家屋が出て、まだ800人程度が避難生活を余儀なくされている。このような中で、またGWの最中に全清連の皆様が熊本に駆けつけていただいて、こんなにたくさんの人と車を出していただいて、ほんとに感謝しています」
「いまの熊本市の状況というのは、1回取っても3日ほどでまた元に戻ってしまう。ごみステーションは全部で2万カ所ありますが、その中で出しやすいところはうずたかくたまっている。取っても取っても取り足りないというところがある。今日皆様に行ってもらうところは、収集がかなり遅れているところや、まだ1回も行っていないところで、役所にも電話が殺到しているところです」
「現場に行くと住民も苦しい状況なので、もしかしたら心ない言葉をかけられたり、これもあれもとお願いされることがあるかもしれません。そこは我慢していただいて、可燃物、不燃物をしっかり分別して仮置き場に収集していただけたらと思います。市民の皆様は自分の近くからごみがなくなるということを、素直に感じられると思いますし、喜ばれると思います。また応援隊が来たということが、復興のひとつのきっかけになって、また頑張ろうという気持ちになると思いますので、今日はよろしくお願いします」と語った。
このあと環境部長から全清連各県連に対して作業地域のエリア分けが説明され、ガススプレー缶を積んでしまうと火災の原因になります。家電4品目も後回しにしようと考えています。といった注意点も示された。住民の反応。感謝を述べる人たち
普段の熊本市は150台ほどの収集車が動いている。しかし地震発生により震災廃棄物に加えて毎日出る家庭ごみも収集しなくてはならない。余力はない。住民からのクレームは多い。手が回らなくて10日も来ていないということになると苦情に発展する。4回線ある電話が全部ふさがっている状態だとも。内容が少しずつ変わってきて、すぐに取りに来てくれとか、なんで来ないんだとなってくるという。だから「なるべくデカイところから集中して崩していかなくては。今日はそういうところをお願いしようと思う」と川口部長。
収集について行くと、「(ごみを急いで持ってきて)これは出していいの?」と尋ねる人。「(ほうきとチリとりを持ってきて)あとは私のほうできれいにしておきますから。ありがとうございます」とお礼を述べる人。「(作業の様子を眺めながら)本当に助かります。ごみが溜まっちゃって、ブラインドカーブがあちこちに。子供が魅かれないか心配だった」とほっとした表情の人。「市とは別の方々なんですよね? 本当にありがとうございます」と頭を下げる人。住民からいろんな声をかけられる。感謝の言葉をかけられると収集作業の方々の顔が思わずほころぶ。
収集した廃棄物は仮置場に集め、そこから焼却や破砕・埋立てなどの処理に向けられる。丸川環境大臣が視察。三井会長とあいさつを交わす。

昼から天候が変化し猛烈な雨風になった。収集の現場では水を吸ったごみが重さを増す。こうした中で丸川環境大臣が被災地の視察に訪れた。三井会長とあいさつを交わし、そのまま清掃工場の中に。
1日の作業が終わり夕食の時間となった。近くの食堂の座敷に全員が集合。ビールが出された。乾杯ではなく、「がんばろう」という発声で杯を空ける。
宿泊所は熊本市から東部環境工場の会議室の提供を受けた。旅館などは地震によって少なからず被害を受け、宿泊できるところは限られ、予約できない状態だからだ。各地の自治体から応援部隊が来ているようだ。この宿泊所では岡山市の直営職員の方々とご一緒だった。寝たい人から順次寝る。時折余震を感じるが、収集作業で疲れているため起き出す人はいない。どこからともなく、かすかにいびきが聞こえてくる。





-

平成27年度の総会の報告
続きを読む: 平成27年度の総会の報告全清連・第六回定時社員総会開催
~会長に三井崇裕氏を再任~
一般社団法人全国清掃事業連合会(全清連)は4月22日(水)千代田区の如水会館を会場に、第六回定時社員総会を開催した。今総会では任期満了に伴う役員改選が行われ、会長に三井崇裕氏の再任を取り決めた。また定款の一部改訂により会長代行職を設け、副会長の野々村清氏(岐阜県清掃事業協同組合理事長)を会長代行に選出した。総会終了後には環境省廃棄物リサイクル対策部の和田廃棄物対策課長の講演が行われ、また席を移しての懇親会には地域廃棄物適正処理推進議員連盟の石破茂会長らをはじめとする多数の国会議員、関係省庁幹部らが出席しての和やかな祝宴が開かれた。
三井会長のあいさつ「防戦から攻勢に出る時期」

午後1時半、定刻通りはじまった定時社員総会は、開会に先立ち全清連の「連合会旗」が入場。全員起立し大きな拍手で迎えた。正面には国旗ならびに全清連の連合会旗が掲げられている。これに向かって一同君が代を斉唱して総会は幕を開けた。
全清連を代表して三井会長があいさつ。本日の総会には初めて出席する会員もいることから三井会長は、全清連という組織の成り立ち、背景ついて少し触れた。平成10年、当時はすべてについて規制緩和せよという大コールが起きていた時期だった。そうした中で7月の日経新聞に、ごみ処理の直営・委託・許可を全部解体して自由にすべきだという記事が出た。当時の総務庁(現総務省)の中に規制緩和委員会というのがあり、そこでそういう意見が出されたのだ。大きな危機感を抱いた全国の同士(岐阜県・鳥取県・広島県・福岡県)が集まり全清連が生まれた。以来17年がたつ。
「あの時に全清連が産声を挙げなかったならば、今頃はいったいどういう状態になっていたのだろうかと考えると、そら恐ろしい感じがします。あの時放置していたならば、おそらくこういう組織はあり得ませんし、また我々の業は相当失われていたことと思います。経済優先の人たちが取り崩しに入ったわけですが、(私どもは)何とか懸命にこらえ、防ぎました。それは皆さんの協力があったからであります。以来17年間の闘いがございます」と三井会長は述懐する。
平成20年6月19日に環境省課長通知(6.19通知)が発出された。「通知の中に、『周知徹底を図られたい』という文言がございます。市町村の公務員の方々が、ふつうならそういうものを読んでくず箱に捨てるところが、それができないという官僚用語です。それで私たちは全国的に新規許可や委託入札の問題とかを大きく改善できると信じていました。問題のある市町村に対して改善を求めて交渉しましたけれども、ほとんどの市町村長がいうことを聞かない。そういう実態に直面してきたわけであります」と述べ、悩みに悩んでいたと胸の内を語る。
そうしたときに追い風が吹く。平成26年1月28日の最高裁判決が出され、それに続いて環境省部長通知が同年10月8日(10.8通知)に発出されたのだ。しかしそれでも理解を示さない市町村がある。そこで三井会長は語る。「全清連の活動は10.8通知を中心に、これを問題のある市町村にいかに改善させていくかというような行動を進めていかなくてはなりません。これをやらないと、何のために心血を注いできたのか。10.8をものにするということは、ここをきちんと押さえて行動をとらなくてはいけません。このことを総会を通じて理解を深めていただきたい」としたうえで、「今まで防戦一方だった。でも組織のおかげで防御してまいりました。しかしこの辺で攻勢に出る時期ではないかなと思っている次第です。そのためには組織を強化していきたい。そのことが私たちの地域の環境保全に大きく貢献する基礎になるからです」と結んだ。平成27年度の事業計画と役員改選

このあと議長に大月伸一副理事長(新潟県一般廃棄物処理業者協議会会長)を選出し議案を審議。第一号議案・平成26年度事業報告?第五号議案・定款の一部改訂を満場一致で承認。第六号議案の任期満了に伴う役員改選では執行理事が選出されたのち、別室にて第1回理事会が開かれ協議。その結果、会長に三井崇裕氏の再任を取り決めたほか、会長代行として野々村清氏を選出した。
再任された三井会長は就任のあいさつで「私も歳を重ねましてこの重責を全うできるかどうか、自信がないような気もしておりますが、腹を括っております。生涯現役でやるぞと自分自身にハッパをかけながら、理事会という強力なバックが控えておりますので皆様に支えていただきながら、全国の業界の、そして私どもが安定した仕事をできるような、地位獲得をしていきたいと思っております」と、出席した230余名の会員を前に力強く語り、支援・協力を訴えた。
なお、平成27年度の事業計画は山田久専務理事が説明に立ち、基本方針を踏まえた形で具体的には以下の9つを示した。
①廃棄物・リサイクル制度に関する対策活動
②地方における10.8通知の周知活動を通した地域の生活環境保全、公衆衛生確保向上のための取組み
④全清連の組織充実強化と団体会員拡大のための活動
⑤地域廃棄物適正処理推進議員連盟との連携強化ならびに支援強化のための活動
⑥会員の啓発ならびに広報のための活動
⑦東日本大震災の被災地への支援活動の経験を活かした活動
⑧一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習会への取組み
⑨東南アジアをはじめとする発展途上国に清掃業務車両(パッカー車、トラック車など)を寄贈する取組み全清連第六回定時社員総会 記念講演
環境省・和田篤也廃棄物対策課長

和田課長の講演内容の柱は、①平成20年6.19課長通知及び平成26年10.8部長通知について。②事業系廃棄物の取り扱いについて。③無許可業者の廃棄物収集運搬業者対策について。④大規模災害時の災害廃棄物対策について――の4本だったが、主に①についての説明に多くの時間を割いた。6.19通知と10.8通知、さらに最高裁判決を加えて、わかりやすく噛み砕いた「解説」といってもよい。また③については違法な不用品回収業者のほか、「遺品整理業」と廃棄物処理法の関係についても言及し、注意を喚起している(続きは全清連会員のみ読むことが可能です)。
石破議連会長「全清連の皆様と力を合わせてやっていきたい」
石破議連会長「全清連の皆様と力を合わせてやっていきたい」

総会終了後には環境省廃・リ部廃棄物対策課の和田篤也課長による記念講演「一般廃棄物の適正処理・3Rの推進について」が行なわれた。このあと会場を移しての懇親会では全清連の地域廃棄物適正処理推進議員連盟会長をつとめる石破茂地方創生担当大臣が駆けつけあいさつを述べたほか、竹本直一副会長、寺田稔事務局長ら多数の国会議員や省庁幹部の祝辞・あいさつが続いた。
石破議連会長は「循環型社会形成推進基本法の理念に従ってやるのだということ、地域地域において信用のある方々、一生懸命努力しておられる方々が、それにふさわしい仕事をしていただく。この2つのことを踏み外さないように、これから先も議連として力を合わせて全清連の皆様と一緒にやらせていただきたいと思っております」と力強い言葉。
乾杯の発声は前衆議院議員の中川秀直全清連特別顧問。容リ法について「要するに(その他プラを)燃やしてしまえというのが半分を超えるのなら容リ法なんかいりませんよ。何が循環型社会ですか。基本法に反する話であって、それなら(容リ法を)見直しする必要はないし、容リ法そのものがいらないということだと思うわけであります」と所感を述べたあと、乾杯の威勢のよい掛け声とともに出席者一同高く杯を上げ、祝宴に入った。第六回定時社員総会開催 資料 <会員限定>
-

平成27年度の全国研修大会実施報告
続きを読む: 平成27年度の全国研修大会実施報告平成27年度『全国研修大会』を開催 誇りをもって国家に貢献
一般社団法人全国清掃事業連合会(全清連・三井崇裕会長)は10月28日(水)午後1時より、東京千代田区の砂防会館において平成27年度「全国研修大会」を開催した。会場には全国から600名の全清連会員らが参集。来賓には地域廃棄物適正処理推進議員連盟会長の石破茂地方創生相をはじめとする31名の国会議員、および関係省幹部が出席し、多くのご祝辞や激励の言葉を頂いた。環境省が廃・リ対策部長名で一般廃棄物処理に関する通知(10.8部長通知)を発出してから1年が経過する今大会、三井会長は冒頭のあいさつで10.8通知をもとにした当該市町村との交渉・協議の必要性をトップに、容器包装リサイクル法の見直しについての考え方、災害廃棄物処理への取組み――といった固形一般廃棄物業界にとって喫緊の課題である3点について述べ、全清連という全国組織としてのあり方を示した。第二部では講演が行われ、環境省の二木豪太郎廃・リ対策部廃棄物対策課基準係長が「一般廃棄物の適正処理に関する諸問題について」説明した。第三部は当面の事業方針の発表、大会決議、スローガン採択等が行われた。

三井会長あいさつ 10.8通知の活用の必要性など3点

研修大会は盛大な拍手に迎えられ全清連の連合会旗入場で幕が開く、大前副会長が力強く開会を宣言し、次いで全員が起立して君が代が斉唱された。
全清連を代表して三井会長が壇上に進みあいさつ。「今日の全国研修大会は、ちょうど昨年、環境省から10.8通知が発出され早いもので1年が経過します」と切り出した三井会長は、3つの要点について述べた。一つ目は16年間をかけて発出を受け止めた10.8通知について。この1年間、全清連として全国各地で問題のある市町村に対して積極果敢に協議を申し入れた結果、相当数が解決の方向に向かっているようだが、まだ十分な理解を得ず、交渉続行中というところも多々あるとの現状を述べた。その上で「問題の市町村とはこれからも誠心誠意をもって交渉を積み重ねることを強く要望します」と全清連会員に訴えた。他方、「私どもは要求することだけでなく、自分たちの正すところは姿勢を正して、BCPの策定、エコアクション21の認証取得、環境法令遵守などの推進を整備し、業務品質を向上させて国家に大きく貢献していかなければならない」とした。
二点目は容器包装リサイクル法の見直し審議について。1年以上審議会が開かれず検討がストップした状態が続いている容リ法制度の見直し議論だが、容リ法も廃掃法同様に「法の目的、趣旨がある。一体この法律は何を求めてつくられたのかということを、(容リに関係する)皆さんが立ち返っていただければ、おのずから回答は出てくるのではないか」と、容リ法の原点に立ち返るべきと強調した。
最後の三点目は災害廃棄物処理に対する業界の取組み。災害発生が多い日本にあって、災害廃棄物処理の推進について環境省から固形一廃の全清連と、同じ一廃の液状の組合にも声がかかった。全清連は東日本大震災にも行き、京都、広島で発生した災害にもその都度出動して懸命に災害廃棄物処理に取り組んできた。いわばこうした場合の現場のプロといえる。こうしたことから会長は「災害時にはわれわれ一廃業者という誇りを持って、国家に寄与してく組織をつくっていきたい」と述べ、「自分のところが災害が起きれば、絆の精神で懸命に、我々ができる仕事はやらなくちゃいかんと思うんです。全清連という全国組織が羽ばたく大きなものが出てきたわけですので、その時には我々は手を携えて頑張りましょう」と結んだ。石破茂議連会長あいさつ「法の趣旨の再確認を」

議員連盟ならびに関係省から多数のごあいさつ、ご祝辞をいただいた。31名の国会議員を来賓として迎えた議連を代表して石破茂議連会長があいさつを述べる。「この議連は何という名前かというと、地域廃棄物適正処理推進議員連盟という名前です。まさしく名は体を表すであって、それぞれの地域において、いかに適正に処理されるかということを推進するのだ、というのがこの議員連盟の趣旨であります。三井会長のおっしゃった法の趣旨というものを、もう一度確認しようというものであります」と議員連盟の名称が表す根幹を説明。そして、「一般廃棄物は自由競争になじまないのだと。なぜなのか。安ければよいという話にならない。その地域、地域の行政が責任をもって適正に処理されるということでなければならない。だとすれば、それは自由競争に委ねられてはならないという法の趣旨を、今一度徹底しなければならないということであります」と論を展開した。
また容リ法についても、「なぜコストが高い方を優先枠として設けているのだろうか。これまた法の趣旨になるわけでございます。リサイクルをするということと燃料にして燃やしてしまうということは、決して同じ話ではないはずだと。法の趣旨はそういうことではないはずだというのが私は原点であろうというふうに思っておりますが、それは同じであるという不思議な主張があるとすれば、それなりの論拠があっておっしゃっているのだと思います。それはどういう論拠でおっしゃっているのか。我々としてなぜ50%優先枠をこれから先も維持していかなくてはいけないのか。何が法の趣旨なのかということをきちんと確認しながら我々は行動していかねばならないと考えています」と法の趣旨の確認を強調した。
そして最後に、「地域においていかにして循環型社会を維持するか、これまた廃掃法の趣旨でございますが、快適な社会として維持することができるのか。その実現に向けて共に努力をしてまいりたいと考えています」と締めくくった。講演会・一般廃棄物の適正処理に関する諸問題について
続いて環境省廃・リ対策部廃棄物対策課の二木豪太郎基準係長による講演「一般廃棄物の適正処理に関する諸問題について」が開かれた。二木係長の講演は、①一般廃棄物処理計画の適正な策定及び運用について、②事業系廃棄物の取り扱いについて、③使用済物品等の適正な処理の確保について、④非常災害時の災害廃棄物対策について――それぞれのポイントなどを説明した。
①については平成20年の6.19課長通知から平成26年の10.8部長通知発出までの経緯や背景を、平成26年1月の最高裁判決などを織り交ぜながら述べた。②では、市町村が事業系廃棄物の取り扱いについて、一廃又は産廃とする解釈を変更する場合は、産廃の適正処理に努めることとされている都道府県に相談した上で、排出事業者への周知を徹底する必要がある。また最近、小規模事業所や商店かなどの事業所から排出される少量プラスチック等を産廃として扱う事例が上がっているが、そうなった場合、小規模事業者に対してマニフェスト交付など排出者責任に基づく様々な規制がかかることに留意する必要があるとした。③は違法な不用品回収業者、引っ越し時に発生する廃棄物の処理、遺品整理に伴う廃棄物の取り扱い、水俣条約を踏まえた水銀廃棄物対策などについて解説。遺品整理については、一般家庭で整理した遺品の中で廃棄するものは一般廃棄物になる。なので、一般廃棄物の収集運搬の許可を得ていない遺品整理業者ができる業務は、依頼を受けた家庭内の敷地内で、遺品を整理するところまで、というポイントを述べた。④では非常災害時における廃棄物処理法の特例として、一般廃棄物の処理の再委託の特例が設定されたことが重要ポイントのひとつと説明した。当面の事業方針
研修会も終盤の第三部に入り、全清連・山田専務理事が当面の事業方針を問題提起という形で発表した。6.19通知と10.8通知がどれほど重みのあるものなのか。しっかりと受け止め勉強する必要がある。10.8通知では最高裁判決(平成26年1月28日)を抜粋してあるが、環境省がこうした抜粋を添付することはかつてなかったことだ。研修大会スローガンにあるように我々は環境省通知に基づき、入札方式導入と新規許可の乱発反対を主張してきた。一部の人間はこれを業界エゴだという。しかしそうではない。環境省通知も最高裁判決もそれを指摘している。国や最高裁の考えとしてそれはある。が、じつはこれは「諸刃の剣」である。最高裁判決にあるように、一廃発生量に応じた需給状況の下における適正な処理が求められている。だから一廃処理業は専ら自由競争に委ねられるべき性格の事業ではない。が、処理量に応じた需給ということでは、許可業者が多ければ削減することも可能になる。我々がそうならないためには勉強して、行政が求めるレベルの一歩、二歩先を行く廃棄物処理、地域住民や議会、行政から信頼され支持される業務品質の向上、達成が必要になってくる。最後に山田専務は「これからの10年。全国津々浦々まで10.8通知を行き渡らせないと我々の未来はない」と締めた。
研修大会はこのあと、大会決議、スローガン採択とつづき、最後は恒例となった「ガンバロー・コール」。こぶしを突き上げガンバローという全員による大きな掛け声が、深まりゆく秋の永田町にこだました。
(研修大会の詳細は、11月下旬発行予定の全清連ニュースに掲載)。 -

平成26年度の全国研修大会実施報告
続きを読む: 平成26年度の全国研修大会実施報告平成26年度『全国研修大会』を開催 実りある成果
一般社団法人全国清掃事業連合会(全清連・三井崇裕会長)は10月20日(月)午後1時より東京千代田区の砂防会館において、全国から全清連会員、地域廃棄物適正処理議員連盟議員、各省庁ら600名を超える関係者の参集を得て平成26年度「全国研修大会」を開催した。今研修大会は記念すべきものとなった。環境省は都道府県・政令市に対して10月8日、廃・リ対策部長名で一般廃棄物処理に関する通知(10.8部長通知)を発出した。本年1月の最高裁判決を踏まえた形でのこの画期的とも思える通知により一廃業界は、長年懸案であった様々な問題を克服していける橋頭堡を築くことができたからだ。三井会長は冒頭のあいさつで、「全清連設立から16年、ようやく私たちの地位の確保ができたものと思っています」と強調した。研修大会は第一部・全清連三井会長ならびに議員連盟、各省庁のあいさつからはじまり、第二部では環境省山本廃・リ対策部企画課長が「一般廃棄物処理に関する今後の取組について」と題して、平成20年6月19日付環境省課長通知(6.19通知)、1月28日の最高裁判決、少量廃プラを含めての事業系廃棄物の取り扱いなどについて幅広く説明。第三部では当面の事業方針、招待団体等紹介、大会決議、スローガン採択――で進められ、出席者にとって非常に価値ある研修大会となった。

三井会長あいさつ「16年かけて勝ち取った成果」

研修大会は盛大な拍手に迎えられ全清連の連合会旗入場で幕が開き、次いで全員が起立して国歌が斉唱された。
全清連を代表して三井会長が壇上に進みあいさつを述べる。「本日の、平成26年度全国研修大会は、非常に意義深いものがあるのではないかと皆さんにご報告したいと思います」と切り出した三井会長は、組織を立ち上げてから16年が経つがこの間、「我々は現行の廃掃法と現場で起きている色々な問題に、悩み抜いた気がしております」と述べ、平成20年には環境省から6.19通知が発出されたものの市町村への周知徹底が十分ではなく、新規許可の問題、委託の入札化の問題、勝手に区分を変更する市町村、また不用品回収の無許可業者の取締り問題等々様々な問題に悩み、苦慮してきた心中を語った。こうした中で今回、環境省から10.8通知部長通知が発出された。「部長通知という過去に例がない出来事です。私たちの業を将来に向かってやり遂げるための非常に大きな担保になると理解しています。これについて我々もずいぶん努力してきたつもりです。議連の方にも相談し、大変なご尽力をいただきました。環境省の方にも現場の声に耳を傾けていただき、10.8通知が出されたものと確信しています。本当に頭が下がる思いです」と述べると会場から大きな拍手が湧き起った。そして「我々はこれを希望として、ようやく16年かかって私たちの地位の確保ができたものと思っています。皆さんと共に闘ってきた成果を認めていただいた。現場の声、それを認めていただいたのをうれしく思います。本日はしっかり研修して価値ある一日でありたい思います」と締めくくった。
野田聖子議連副会長あいさつ「思いを引き継ぎ周知徹底の運動を続けていく」

議員連盟ならびに関係省庁から多数のごあいさつ、ご祝辞をいただいた。議員連盟の石破茂会長は地方創生特別委員会のため出席かなわず、代わって議連を代表して野田聖子議連副会長があいさつを述べた。「平成20年に6.19通知が発出されましたがこの間、市町村によって相当温度差があってまったく聞く耳も持たない地方自治体も発生していると。現場にいらっしゃる皆様方は苦しい思いをしてらっしゃったと思います。で、全清連、議連がしっかり力を合わせて、廃掃法の原理原則を全国の自治体に浸透させていかなければならないということで今日を迎えたわけです。前会長の中川先生が必死にお取組いただいたこの精神を引き継ぐべく石破先生のもと、全清連の皆様と勉強会を通じていろいろと学ばせていただきました。まだまだ力不足かもしれませんが精一杯努力を続けてきたところであります。結果、最高裁での判決を受けて、このたび平成26年10月8日に部長通知という形で重たい通知が出たことは皆様方に申し上げるまでもないことと思います。今後、三井会長はじめ、16年間頑張ってこられた思いを絶やすことなく、私たちが引き継いで全国津々浦々、周知徹底にいそしんで、現実のものとしていく運動を続けていくことを議連を代表してお約束いたします」と語った。斎藤鉄夫議連幹事長や議連国会議員のあいさつが続く。
省庁からは環境省、経産省、農水省の幹部があいさつに立った。環境省の鎌形廃・リ部長は、最高裁判決が示されたことに加えて一廃処理に関連した大規模な不適正処理事案が、いまだ解決をみないまま長期化していることから「今般、廃棄物処理法の目的、周知を改めて都道府県、政令市のトップに周知するため10月8日付で部長名で通知を発出した。今後様々な機会をとらえて実務に携わる方々にも周知徹底を図ってまいります」と述べた。
また最後に中川秀直全清連特別顧問が「最高裁判決にありますように、皆様のお仕事は非常に公共性が高い。品質向上とか業務の確実な履行とか、本当に国民、地域住民から信頼されるような仕事を皆でつくりあげていかないといけないと思います。そして議連の皆様方、地域で皆さんと勉強して共々、いい方向に行くというのが重要と思います」と、まとめのあいさつ。講演会・一般廃棄物処理に関する今後の取組について

続いて環境省廃・リ対策部企画課・山本課長による講演「一般廃棄物処理に関する今後の取組について」が開かれた。1900年(明治33年)に制定された「汚物掃除法」から1970年(昭和45年)の廃棄物処理法、そして平成に入った1990年代から今日までの廃棄物問題の変遷を説き起こし、時代が変わろうとも、行政が移り変わってもその底流には常に「衛生問題がベースとしてしっかりあるということです」と説明する山本課長の講演は、「一般廃棄物の市町村処理責任について」「6.19通知」の意味、本年1月28日の「最高裁判決」、少量廃プラを主体とする「事業系廃棄物の取り扱い」など広範囲にわたり、丁寧かつわかりやすく解説した。さらに会場との質疑応答は一般廃棄物処理業者にとって、廃棄物処理法に位置づけられた自分たちの業を理解するうえで非常に参考になるものだった(くわしい内容は全清連へお問い合わせください。)
当面の事業方針
研修会も終盤の第三部に入り、全清連・山田専務理事が当面の事業方針を問題提起という形で発表した。「10.8部長通知という画期的なものが出されましたが、これからが正念場。これをいかに活用していくかです。行政は法律がまったくわかっていないから我々を無視したことをやる。廃棄物処理法はこういう特別なものですよ、という運動をやっていかなくてはならない。で、環境省がこういう資料を出してくれたから、(我々は行政に対して)説明することができるという形になってきたということです。全清連はここに価値がある。お互い理解して地元の方々に支持されることが大事になる。明日からいい仕事をしましょう」と気を引き締めつつ総括した。研修大会はこのあと、新規入会会員(栃木県小山市と兵庫県川西市の一廃業者)の紹介、大会決議、スローガン採択とつづき、最後は恒例となった「ガンバロー・コール」を全員で行い幕を閉じた。
(研修大会の詳細は、11月下旬発行予定の全清連ニュース第73号に掲載)。

活動報告
活動報告
activity