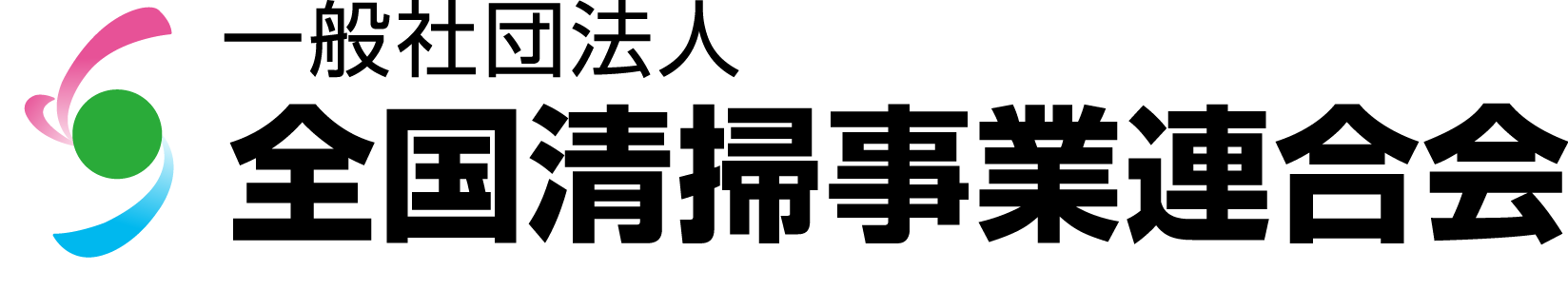-

平成21年度の全国研修大会実施報告
続きを読む: 平成21年度の全国研修大会実施報告平成21年度「全国研修大会」盛大に開催

「環境保全優先、安心・安全の循環型社会を目指そう!」をメインスローガンに全清連は10月16日、平成21年度の「全国研修大会」を盛大に開催した。会場の東京千代田区の砂防会館には全国から600名を上回る会員が参集した。今大会では、民主党が先に発表した政策集の中に一廃・産廃の「区分見直し」が盛り込まれており、事業系一廃の産廃化が懸念されることから、これに反対する取組みなどを事業計画とした。また昨年6月19日に環境省が各市町村に向けて通知(6.19通知)した「ごみ処理基本計画の策定指針」の周知徹底運動を引き続き進めていくことも確認した。
全清連三井崇裕会長のあいさつに続き、地域廃棄物適正処理推進議員連盟である多数の衆参両議院の国会議員の祝辞、環境省・南川大臣官房長ほか経産省、農水省のあいさつが述べられた。
講演は環境省廃棄物対策課・名倉課長補佐の「平成21年版 廃棄物処理法の解説」。また「地域活動の事例発表」として、「環境とちぎ協同組合青年部の今後の取組みについて」(環境とちぎ協同組合青年部)、「愛知県田原市における委託業務の競争入札撤回実現の取組みについて」(愛知県地域環境創造協会)など4件の報告がされた。全清連としての当面の事業方針が述べられ、新規加入団体の紹介が行なわれるなど有意義な全国研修大会となった(詳細は全清連ニュースに掲載)。
-

平成21年度の総会の報告
続きを読む: 平成21年度の総会の報告第11回通常総会開催
~一般社団法人設立へ、6.19通知の周知活動の推進~

全清連の第11回通常総会は4月24日(金)午後1時半より東京千代田区の「如水会館」を会場に、連合会会員243名の出席を得て盛会に開催した。今総会では議案に平成20年12月から施行された新公益法人制度を踏まえて、全清連の一般社団法人化への設立申請が上程され、これを含めてすべての議事は審議の結果、満場一致で可決された。21年度の活動方針としてはとりわけ、昨年6月19日付で環境省から発出された「ごみ処理基本計画の策定指針」(6.19通知)の意味と意義を、各県単位での研修会などを通じて各市町村に周知すべく活動を推進する。それによって、全国的に広がりをみせつつある新規許可の乱発、委託業務の入札化などの未然防止に傾注していく。全清連は新しい10年に向けて活動を開始した。
三井会長、重要な事業計画として3点を述べる

総会は川合副会長が出席人数を確認、定款に基づき総会が成立した旨の開会宣言のあと、三井会長があいさつ。三井会長は全清連の事業計画のなかでも重要とされる3点をあげた。
ひとつは6.19通知の件。「この通知が出されるまで皆さんとご一緒に何年もかけて環境省と交渉を行ってまいりました。それが出されたことは(全清連にとって)大きな成果だというふうに自負しております。内容は、昨今希薄になりがちだった環境保全、公衆衛生の向上を廃棄物処理法の目的としているすばらしいものであります」と重要な通知であるが、にもかかわらず一方で、この6.19通知の内容が市町村に浸透していない現実がある。そのため「私どもは市町村に向かって、6.19通知の取り扱いをどうするのかという活動をしないと、この文言は絵に描いた餅になる危険性がある」とし、「各県単位で積極的に活動を展開してもらいたい」「県下の市町村に対して(6.19通知を)どのように考えるか。たとえば、新規許可の乱発、委託業務の入札、この大きな問題のストッパーとして6.19通知は出された。私どもは少なくともそう認識すべきだと。この通知を最大限活用したい」と強調した。
二つ目は規制改革会議の第3次答申の件。昨年12月22日に出された第3次答申には「まだ廃棄物処理法の定義・区分に触れるようなことが書かれている。一廃処理は規模を拡大して広域化すべきであるという視点で出されている。我々全清連としては、力を結集して注視していく必要がある」
三点目は全清連の一般社団法人化の件。「10年かかりましたが、全清連は一般社団法人として申請することになります。執行部が皆様に約束してきた懸案事項のひとつであり、嬉しく思っています」と述べた。講演会の質疑応答では「現場の声を聞いてほしい」との注文も
通常総会終了後には「一般廃棄物行政の動向」というテーマで、環境省廃・リ対策部廃棄物対策課の橋詰課長による記念講演会が開かれた。橋詰課長は一般廃棄物の適正処理、3Rの推進などについて解説し、さらに現在国の審議会で議論されている廃棄物処理制度に関する論点なども説明した。が、会場との質疑応答では、今年全清連に入会したという柏原市(大阪)の処理業者から、「国の審議会はもっとゴミ行政の現場の声を聞いてもらいたい」との要望が出された。
柏原市は平成23年度から、委託制度を改め入札制度に切り替えようとしている。この業者は、「私どもは50数年間、忌み嫌われるごみを委託という形で処理してきた。この50年間、市もかなり潤ったと思う。そうして努力してきて、いま使い捨てカイロのように経済性ということで入札制度にしようとしている。きれいな街づくりということで昼までに収集することを条件としてやってきた。しかし入札では午後5時までとなっている。これではカラスや野犬にごみ袋を破られ、廃棄物処理法の目的とする環境保全、公衆衛生は堅持できない」と現況を述べ、国の審議会ではこうした現場の声を反映した議論を求めた。
総会終了後の懇親会では来賓に地域廃棄物適正処理推進議員連盟会長である中川秀直議員、議員連盟副会長の北側一雄議員をはじめ、寺田稔議員、木挽司議員、平口洋議員、吉村剛太郎議員、魚住裕一郎議員、塚田一郎議員ら地域廃棄物適正処理推進議員連盟の国会議員を迎えあいさつが述べられ、環境省谷津廃・リ部長、農水省増田食品産業企画課長、経産省横山リサイクル推進課長らも出席しての歓談が続いた。
全清連平成21年度の事業計画
事業の基本方針は以下の4点。
①廃棄物・リサイクル制度に関する対策活動の推進
②地方における6.19通知に係る周知活動の推進
③全清連組織の拡充強化
④啓発活動の積極的推進第11回通常総会 資料 <会員限定>
通常総会 記念講演「一般廃棄物行政の動向」
環境省廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課 課長 橋詰博樹 殿 -

平成20年度の全国研修大会実施報告
続きを読む: 平成20年度の全国研修大会実施報告平成20年度全国研修大会盛大に開催 “6.19通知の周知徹底を!”

全清連の平成20年度「全国研修大会」が10月20日、東京千代田区の砂防会館で全国から600名を超える会員が参集し盛大に開催された。先の6月19日に環境省廃・リ対策部廃棄物対策課長名で発令された新「ごみ処理基本計画策定指針」通知(6.19通知)は、業界にとって画期的な出来事だった。大会では6.19通知を確認し、市町村に対して通知徹底の働きかけをしていくことを当面の事業方針のひとつとした。
冒頭、三井会長が「ごみ処理基本計画策定指針の通知が出されたのは全清連会員である皆様の努力によるもの。ありがとうございました」とあいさつを述べると会場から盛大な拍手が沸き起こった。野田聖子衆議院議員、武藤容治衆議院議員、吉村剛太郎参議院議員ら多数の衆参国会議員の祝辞、環境省廃・リ対策部の谷津龍太郎部長ほか、経産省、農水省からのあいさつが続いた。
講演は環境省廃棄物対策課・秦康之課長補佐の「一般廃棄物行政の動向について」。この中で秦課長補佐は6.19通知を発した背景や意味、ポイントなどについて触れ、参加会員との間で活発な質疑応答が繰り広げられた。また「地域活動の事例発表」として、「環境省が発出した6.19通知のもたらす意義と課題」(広島県清協)など4件の報告が行なわれたが、会員がどのようにして6.19通知を捉え、そしてそれをどのようにして市町村に周知徹底を要望していくのか――。事例発表はこうしたことに応えるケース・スタディーとして大変参考になる内容といえる。 全清連としての当面の事業方針が述べられ、熊本県、山口市、高松市、島根県、三重県などの新規加入団体や、加入を検討している団体の紹介が行なわれるなど有意義な全国研修大会となった(詳細は全清連ニュースに掲載)。
-

平成20年度の総会の報告
続きを読む: 平成20年度の総会の報告第10回通常総会開催
~結成10年の節目迎え、新たな活動のスタート~
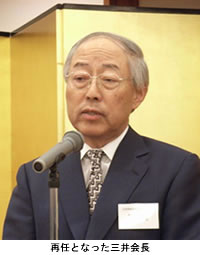
全清連の第10回通常総会は4月23日(水)午後2時より東京千代田区の「如水会館」において、連合会加盟会員210名の出席のもと開催した。第1号議案・平成19年度事業報告承認の件など議事は審議の結果、すべて満場一致で可決。役員改選では、会長に三井崇裕氏(広島県)、副会長には川合清和氏(岐阜県)、西山末男氏(福岡県)、専務理事に山田久氏の再任をとりきめたほか、理事12名、監事2名を選出した。
再任となった三井会長は、多発している市町村の新規許可乱発、随契から競争入札への切り替え問題について触れ「こうした大きな問題をどうしても解決しなければいけない。不退転の覚悟でのぞむ。次の世代、若い人たちに良好な環境を提示するのが私たちの務め。大きな問題の片をつけたい」と強調。結成10年という節目を迎え、全清連は新たな活動のスタートを切った。

総会終了後の懇親会では来賓に寺田稔議員、竹本直一議員、武藤容治議員、野田聖子議員、根本匠議員ら地域廃棄物適正処理推進議員連盟の国会議員12名を迎え、環境省由田廃・リ部長、農水省川合食品産業企画課長らも出席して和やかな歓談が続いた。また今回は全清連顧問弁護士、芝田稔秋先生による記念講演「一般廃棄物処理事業の本来のあり方」も行なわれた。
平成20年度の事業計画
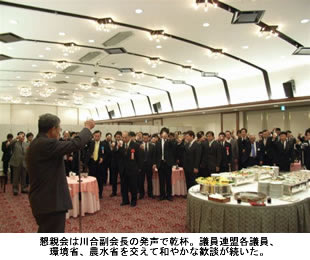
事業の基本方針は以下の4点。
①廃棄物・リサイクル制度に関する対策活動の推進
②地方における新規許可乱発、入札方式導入等の諸問題に係る対策活動の推進
③全清連組織の拡充強化
④啓発活動の積極的推進
事業計画のなかで特に大きなテーマとなるのが新規許可乱発と入札方式導入である。この問題は発生した時点で、すでに押し込められた状況と考える必要があり、既成事実化される危険性がある。平素の行政へのかかわりのすべてが問われる。各県連組合は平素からその危機意識を組合全体で共有するとともに、現状の理論展開・組織団結力・交渉力の底上げを図らなければならない。
こうした新規許可乱発や入札方式の導入が生じないようにするためには、全国都道府県すべてにおいて一廃処理業界の団体を組織し対処する必要がある。知らないところで、知らないうちに一廃処理業界の存立基盤が崩れていくことを防ぐために、またそのことを防ぐための全清連の影響力を高めるためには、組織の拡充強化は全清連会員一人ひとりが全力で取組まなければならない活動である。『一般廃棄物処理事業のあり方』 ~全清連第10回通常総会記念講演より~
講師:芝田稔秋弁護士
去る4月23日に開催された全清連第10回通常総会では、講師に芝田稔秋弁護士を迎え「一般廃棄物処理事業のあり方」と題しての記念講演が行なわれた。市町村が一般廃棄物処理を委託する場合、「競争入札と随契のどちらがベターなのか」(芝田弁護士)という話が中心になり、競争入札と随契のそれぞれを比較して特長や長・短所を検証。そのうえで結論を導き出した。以下、講演要旨を掲載する。
第10回通常総会 資料 <会員限定>
-

平成19年度の全国研修大会実施報告
続きを読む: 平成19年度の全国研修大会実施報告平成19年度全国研修大会盛大に開催 砂防会館に600名が参集

「環境保全優先、安心・安全の循環型社会を目指そう!」をメインスローガンに全清連の平成19年度「全国研修大会」が10月12日、東京千代田区の砂防会館で盛大に開催。会場は全国から参集した600名を上回る全清連会員で膨れ上がった。
全清連三井崇裕会長のあいさつに続き、議員連盟会長で元自民党幹事長の中川秀直衆議院議員をはじめ衆参両議院から23名の国会議員の祝辞、環境省廃・リ対策部の由田秀人部長ほか経産省、農水省のあいさつがつづく。
講演は環境省廃棄物対策課・関荘一郎課長の「市町村の3R化改革について」。関課長と会員との間で活発な質疑応答が展開され、一般廃棄物処理の認識を新たにした。また「地域活動の事例発表」として、「広島市における新規許可問題への取組みとその後」(広島清掃事協組)など2件の報告がされた。全清連としての当面の事業方針が述べられ、新規加入団体の紹介が行なわれるなど有意義な全国研修大会となった(詳細は全清連ニュースに掲載)。

活動報告
活動報告
activity